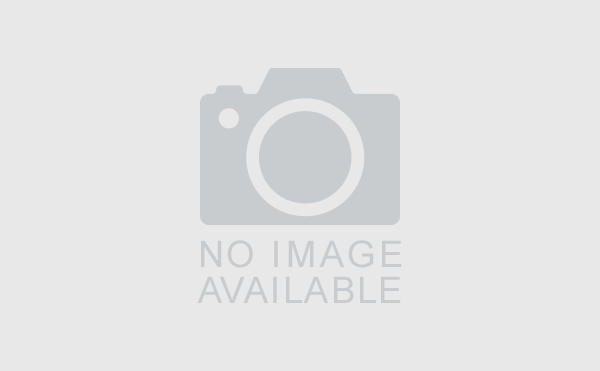令和5年第2回定例会 2023-06-12(録画中継と議事録抜粋)
- 子どもの権利、学校の校庭の整備、安全・安心のまちづくり等について
・子どもの権利について
・学校のグラウンド整備について
・安全・安心なまちづくりについて - インターネット中継
https://musashino-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=2473 
- 議事録
◯6 番(宮代一利君) 6番、会派ワクワクはたらく、宮代一利でございます。2期目に入りました。前向きに取り組んでまいります。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
子どもの権利条例が制定されました。条例制定までたくさんの委員会を開催し、アンケートも実施し、特に子どもの意見も数多く聞き、丁寧なつくり込みをしていただき、制定に至ったと認識しています。当然のことですが、条例は制定が目的ではなく、制定がスタートで、それを実行していくことが大切です。子どもの最善の利益を優先し、全ての子どもが幸せになることを強く望みます。
先日、武蔵野市青少年問題協議会地区委員会委員委嘱式に参列しました。記念講演会が開催され、小山亮二さんによる、「子どもの主体性を引き出す遊びとの関わり方」という題の内容について聞きました。講演会を聞くというよりは、参加型のワークショップのようなものでした。市長、教育長、各部長、そしてこちらにいらっしゃる議員の皆さんの数多くも参加していて、真剣にじゃんけんをして盛り上がりました。とても楽しい活動だったというふうに思っています。
小山先生は一般社団法人あそび庁の代表理事です。あそび庁とは、遊びを通じて、子どもたちや大人が生涯にわたりウエルビーイングを育むことができる社会の実現を目指す活動をしています。まず遊びの価値を高める。次に子どもも大人も本気で遊べる環境をつくる。環境とは、人材、物、場所、制度など様々です。さらに日本の遊び文化を世界に発信する。こういったことに取り組んでいる団体です。
今回の講演会を経験して感じたことは、楽しく遊ぶことを伝え、牽引することは、リーダー、指導者のスキルが非常に強く影響するということです。小山さんの声がけで、大の大人がたわいない遊びに夢中になっていく姿を目の当たりにしました。
私は少年サッカーの指導に24年携わってきましたが、この現場においても同様のことが言えます。指導者の声がけ一つで選手たちの動きが変わります。「そこ、しっかりプレーしろ。練習でやったとおりきちんとやれ。ゴールを決めろ」。かつて指導者のこんな大きな声がグラウンドに響きわたったこともありました。その声で選手がはっと目覚めてまた頑張る。そんな流れを信じていた時代だったのかもしれません。私の育った昭和の時代はスパルタ時代で、根性論が横行していました。今でも昭和育ちの指導者がいて、その人にしみついたやり方はなかなか変わらないという側面もあります。
一方で、指導理論に注目して改革をしようという動きも活発化していて、一例として、日本サッカー協会が展開している、指導者の指導に関する内容は目覚ましい進歩を遂げています。プレーしている選手の様子をじっと見届け、ベンチに戻ってきたときに、さっきのプレーはどんな判断だったのか、考えを聞かせてくれと、まず考えを聞くこと、そしてその考えをベースに、よかったこと、課題を整理していく。こういった指導を続けることにより、選手との信頼関係が築かれ、選手のやる気が増しつつ実力もアップする。そんな時代になってきていると感じます。指導のスキルという言い方をしましたが、大人がよく学び実践することが求められているということだと感じます。
さらに言えば、子どものやる気を引き出すためには、大人は冷静でなくてはいけないということです。なかなか難しいことです。各御家庭における育児においても同じことが言えると思います。思わず感情的に怒りを爆発させてしまう瞬間もあると思います。
まちなかで見かける光景の一つです。駄菓子屋さんの店先には、子どもにとってきらきら光る魅力的なおもちゃが並んでいます。思わず触りたくなり、子どもは手を伸ばします。その瞬間、「触っては駄目。いつも言っているでしょう。何で分からないの」。店頭のおもちゃを触ってはいけないと教えるのは、しつけと言えるかもしれません。しかし、「いつも言っているでしょう」。これは、大人が自分の考えを押しつけている、しかし子どもは聞いていない、納得していないという状態です。伝え方に問題がある。もっと工夫が必要と考える場面ではないでしょうか。そして「何で分からないの」という一言。これは子どもの発言を促す質問になっているでしょうか。単なる罵声になっていないでしょうか。子どもに何かを伝えるには、相手の年齢、理解度に合わせて、時間をかけることが大切だと思います。
子どもの権利条例を実効性あるものにするためには、子どもの最善の利益を守るために、そこに向けて大人が学ぶことが必要だと思います。あえて昭和という時代の話をしましたが、時が流れ、今は令和の時代です。しかし、まだまだ様々な場面で昭和の影響が残っているとも言えます。一方、新しい時代の波も確実に押し寄せてきていることも実感しています。
例えば子どもの権利を守ることについて、大人が会話のスキルを磨くこと。アンガーマネジメントのスキルを磨くことが大切だという言い方をしますが、実は、これは単なるスキルにとどまらないのかもしれないという感覚もあります。国民性といいますか、国の文化というものとして醸成されていけば、国そのものが変わることができるのではないかと思うということです。今回の子どもの権利条例の制定を機に、武蔵野市において、子どもの権利を守ることに多くの市民が目を向け、自ら学び、実践する、そんな自治体に育っていくことができたらよいと感じています。
以上の考えに基づき、学校における子どもの権利条例へのアプローチについて伺います。アプローチ先は、まず生徒児童が対象となるのは当然ですが、保護者もアプローチ先としては重要と考えます。生徒児童には、授業の中で子どもの権利に関するプログラムが組まれることになりますか、また、保護者にはどんな方法で伝えていきますか。
さらに先生への浸透も必要だと考えます。学校の現場は学習指導要領に沿って授業が進められていますが、これまでの教育に対する考え方と子どもの権利という考え方は、方向性として一致しているのでしょうか。指導要領が存在し、それに縛られている状況において、先生は授業を進めなければならない。とにかく限られた時間の中で教えなければいけないという考えになる。
しかし、児童生徒はその流れに疑問を感じたり、何となくしっくりこないという場面もあると思います。まさに子どもの権利を守るためには、そんな子どもの気持ちに寄り添い、言葉に耳を傾けることが必要なのではないでしょうか。きっと時間がかかることだと思います。児童生徒が前を向き、静粛に授業を聞くことが前提となっていた昔の教育方法で、子どもの権利を守ることはできるのか、そこに課題があると思います。
校則という決まりもあります。クラスによって先生が決めたルールもあります。そして自主的に児童生徒がつくったルールもあるかもしれません。今後子どもの権利を守るために、こういったものを整理し、見直していくことが必要だと考えます。
質問の内容をまとめます。
質問1の1、子どもの権利条例を浸透させることについて。
1)学校における児童生徒へのアプローチの方法について伺います。
2)先生自身が理解を深めるための具体的な取組について伺います。
3)保護者へのアプローチの方法について伺います。
質問1の2、子どもの権利の本質について。
1)家庭におけるしつけ、学校におけるルールなどが、子どもの権利を守ることと矛盾する可能性があるという考えに関する見解を伺います。
2)子どもの権利を守るために大人が学ぶべきことについての見解を伺います。
次に、学校のグラウンド整備についてです。
先日報道で、杉並区立荻窪小学校が取り上げられていました。おやっと耳を傾けました。実は私の母校なのです。ところが残念なことに、そのニュースの内容は、体育の授業中に児童が転倒し、地面から突き出していたくぎで、左膝付近に十数針を縫う裂傷を負ったというものでした。校庭の地中に埋まっていたくぎは、運動会などでラインの目印となるマーカーを固定する際に打ち込んだものとのことです。私が関わっているサッカークラブでも、同じ様式のマーカーを使用していました。今年の5月には運動会が開催されましたので、それに間に合わせて、急ぎ、全てのくぎを抜きました。
かつて、グラウンドでバレーボールやテニスをしていた学校もあると思います。ネットを立てるために地面に器具を埋め込んでいた時代もあり、その残留物はもうきちんとなくなっているのか、類似するくぎだけではなく、類似するリスクもあると感じています。自治体によっては、金属探知機を用いて調査をしたという話もあります。まず、武蔵野市内の学校における現在の状況について伺います。
質問2の1、市内の学校における校庭の現状について、以下伺います。
1)金属のくぎ──ペグです──を使用したマーカーを今まで使用してきたか。
2)市内の学校で、現状に関する調査を今回実施しましたか。
3)調査により、くぎの残留の本数など、把握していることがあったらお教えください。
以前から、学校の校庭の整備については課題になっていたと認識しています。クレイ──土です──の校庭は、時間の経過とともに砂が細粒化──細くなる──すると言われています。実際雨の後の水はけが悪くなり、また雪が降るとぬかるみ、数週間復帰しないという状態になります。定期的に表層を削り取り、新しい土を入れるのが、適切な整備方法と考えます。
質問2の2、校庭の整備に関する考え方について。
1)校庭の整備を実施するタイミングに関する判断基準について伺います。
2)今後、計画的、定期的な整備が必要と考えますが、見解を伺います。
3つ目です。令和5年第1回定例会の代表質問において、ブルーキャップについて、松下市長から、令和4年「4月につきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例の一部改正によって、客引き行為、スカウト行為及び客待ち行為を新たに禁止行為として追加した効果は、一定はあると考えられるものの、ブルーキャップがその場を離れた際や活動時間後、早朝時間帯にも客引きや客待ち行為を行う方がいらっしゃるという課題については認識をしております。活動時間の延長や運用の見直しにより、禁止行為が行いづらい環境というのを目指してまいりたいと思います」と御答弁いただきました。
また、「安全・安心なまちづくりについてです。客引き、客待ちの実態に即応する形で、ブルーキャップや吉祥寺ミッドナイトパトロール隊の運用を見直しながら、禁止行為がなくなるようなというか、行いづらい環境づくりというのを目指していきたいと考えております」との答弁をいただきました。
令和5年度からブルーキャップの委託事業者が替わったと認識しております。まず新しい事業者の選定について伺います。
質問3の1、ブルーキャップの委託事業者について、選定の方式について伺います。
1)一般競争入札でしょうか、それとも違う方式でしょうか。
2)選定における審査基準について伺います。選定の審査基準について、条例が新しくなったことにより、事業者の機能が変化したと思います。それに対応して事業者に期待する内容も変化しているはずで、今回の選定によってどんな変化が期待されるのか。さらに、4月に事業者が切り替わってから既に2か月余りがたっています。この間の実績とその評価についても伺います。
質問3の2、今後の取組についてです。先ほど第1回定例会での市長の御答弁を紹介しました。課題は認識している、活動時間の延長や運用の見直しを行い、そして禁止行為が行いづらくなる環境を整えるとの内容でした。私も路上喫煙を注意している現場に居合わせましたので、徐々に変わってきたなという印象を持っています。またブルーキャップのみならず、ミッドナイトパトロールとの連携にも触れていました。今後の展開に期待しています。以下質問します。
1)これまでに改善した活動内容について伺います。
2)さらに実効性を高めるために、今後取り組む内容について伺います。
以上、壇上からの質問といたします。
-
78:
◯市 長(松下玲子君) 宮代一利議員の一般質問に、順にお答えをいたします。
まず、私への質問は質問1の2の1)についてです。家庭におけるしつけ、学校におけるルールは、本質的には子どもの権利を保障するためのものであると考えております。しつけやルールは子どもの権利を侵害するものではなく、子どもが未来にわたって自分以外の様々な人々と関わり合いながら、安心して生き、自分らしく育ち、社会において自立していくために、子どもに必要な行為や決まり事であると考えております。
保護者や学校の関係者は、家庭におけるしつけや学校におけるルールなどが、子どもの権利をきちんと保障するための行為や決まりになっているか、子どもの最善の利益を第一に常に心がけていくことが大切であると考えます。
2)についてです。子どもの権利を保障していくために、まず大人が、子どもにも大人と同じように権利、基本的人権があるということを理解し、子どもに相対していくことが大切であると考えます。その上で、自分の権利とともに、ほかの人の権利もかけがえがなく大切であるという認識に立ち、目の前にいるその子どもにとって最もよいことは何なのか、まずはその子どもの声を聞くところから始めることが大切ではないかと考えております。
続いて、3の1の御質問についての1)についてです。指名型企画提案方式によるプロポーザルにて委託事業者の選定を行いました。なお、ブルーキャップと吉祥寺ミッドナイトパトロール隊の業務について、一括してプロポーザルを実施いたしました。
2)についてです。技術点と価格点の総合評価により優先交渉権者を決定いたしました。技術点の主な評価項目は、業務に対する理解度、類似する業務の実績、吉祥寺駅周辺地域の現状分析や客引き行為等を行う者への対応方法、従事者の体制などであります。
3の2の御質問についてです。その1)についてです。令和5年度からブルーキャップの活動時間を延長するとともに、深夜、早朝に活動する吉祥寺ミッドナイトパトロール隊においても、従来の安全パトロールに加えて、客引き行為等に対する指導等ができるよう制度を変更し、より体制を強化いたしました。またブルーキャップの活動人数について、客引き行為等を行う者が多い金曜日の夜間等に、より多く隊員を配置するなど、曜日や時間帯による人数を工夫し、より効果的なパトロールが実施できるよう運用しています。
2)についてです。つきまとい勧誘行為など禁止行為に対しては、毅然とした態度で注意や指導を行うとともに、条例について知らない者に対しては丁寧に内容を説明するなど、粘り強く活動を行うことで、禁止行為が行いづらい環境づくりを目指してまいります。
他の質問については、教育長からお答えをいたします。 -
79:
◯教育長(竹内道則君) 私からは、子どもの権利条例の浸透についてと学校のグラウンド整備について、御質問にお答えいたします。
まず初めに、子どもの権利条例を浸透させるための学校における児童生徒へのアプローチ方法についてです。市内全小・中学校に向けて、この4月に「こどものけんりってなぁに?」の第6号を送付し、学習者用コンピューター上で全ての子どもたちが閲覧できるようにしています。また、市報むさしの、武蔵野市子どもの権利条例制定特集号のデータを各校に送付しているところです。
また校長に対して、4月の全校朝会などで子どもの権利条例について触れるよう指示しているところでございます。今後、社会科の小学校6年生、子育て支援の願いを実現する政治の単元や、中学校3年生の地方自治と私たちの単元などで、自分たちの大切な権利として子どもの権利について触れることも促しております。
こうした取組を通して、各校で児童生徒に子どもの権利条例について周知し、その趣旨が浸透するよう努めております。
続いて、子どもの権利条例について、先生自身が理解を深めるための具体的な取組についての御質問ですが、定例校長会で子ども子育て支援課による説明機会を設けるとともに、先ほどお話しした市報特集号を配布し、各校で子どもの権利条例についての理解を深めるための研修を実施しているところです。
また、教務主任会や生活指導主任会などの学校運営の中核となる教員に対して、教育委員会から条例の趣旨について研修を行っているところです。それぞれの各主任は研修内容を自校に持ち帰り、条例の趣旨について自校で伝達することで、さらに教員の理解が深まるよう努めているところです。
次に保護者へのアプローチの方法についてですが、学校だよりや保護者会等を通じて保護者への周知を実施しているところでございます。
続いて、家庭におけるしつけ、学校におけるルールなどが、子どもの権利を守ることと矛盾する可能性があることについての御質問ですが、例えば校則は校長により制定されるものではありますが、令和4年12月、昨年の12月、12年ぶりに改訂された生徒指導提要では、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいであるとか、その見直しに当たっては、児童会、生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり議論したりする機会を設けると、児童生徒の関与や意見を聴くことを新たに示されています。
校則を含めて学校におけるルールについても、子どもの権利条例の第17条や18条に示されているとおり、子どもが自分の意見を表明することや意思決定の場への参加を推進するなど、子どもたちに身近な課題を自ら解決するといった機会を設けるよう促していくことは、今後の学校教育や生徒指導の充実において大切だと考えております。
次に、学校のグラウンド整備について、学校の校庭のくぎについての御質問です。杉並区の事故の報道に触れて、各校では直ちにそれぞれ校庭の状況を自ら点検し、不要なくぎは除去するなど、必要な対応を行っているところです。
金属のくぎを使用したマーカーを使用してきたかの御質問については、マーカーにはプレート状のもの、プラスチック製のもの、また学校施設開放でスポーツ団体が使用するものなど、様々なものがあり、金属のくぎを使用したマーカーも使われてきました。
市内の学校で現状に関する調査をしたかの御質問ですが、先ほど申し上げたとおり、各校それぞれで点検は行われておりましたが、教育委員会からも改めて注意喚起するとともに、全体を把握するため、各校の状況を確認したところです。
そしてくぎの残留の本数と実施した処置の御質問についてですが、現在も50メートル走のライン引きの目印やハードルを設置するための目印など、日常の教育活動に必要なマーカーは残っています。残っているものの個数はカウントしておりませんが、教育委員会の職員も現地に行き、完全に固定され、安全であることを確認しております。
そして校庭の整備を実施するタイミングに関する判断基準についての御質問ですが、平成18年度から各校において、雨水貯留浸透施設の設置が順次進められてきました。校庭の整備についてはそのタイミングに合わせて行ってきたところです。
今後、計画的、定期的な整備が必要と考えるが見解を伺うとの御質問ですが、今後については、雨水貯留浸透施設の設置がほぼ完了していることから、過去に校庭整備を行った順を基本に、実際の校庭の状態や学校の改築順なども考慮して、必要性を精査した上で整備を行っていきたいと考えているところです。
以上でございます。 -
80:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございました。まず、最後のグラウンドの話を先にやります。
まずいろいろ点検をしていただいたということで、よかったと思いました。ただちょっと気になったのは、くぎ型のペグのものも今も使っていることです。きちんと固定されているということで、それにオーケーを出しているというふうに受け止めてしまったのですが、プラスチック製のものがあったり、平板状の陶器状のものとかもありますので、それに切り替えていったほうがいいのではないかなと感じるのですが、その辺いかがでしょうか。
実は我々育成団体も、くぎをやめてと逆に言われるのではないかなと思っていて、次にやるのだったらプラスチック状のものにしてくださいというような指示が出るかなと思って、待ち構えていたところなので、ちょっとそこは見解を伺いたいなと思います。
もう一つ、雨水浸透ますのタイミングと、それから学校改築のタイミングというのは、きっとそう来るだろうなと思っていたのですけど、グラウンドの整備のタイミングのほうが、もう少し定期的に、短いスパンなのではないかなというふうに考えているのです。やはり先ほどの細粒化の問題。地面の砂がどんどん細くなっていって、舞ったりするようなことがあったりとか、雪が解けにくくなるような現象も起こっているので、グラウンドはグラウンドで、もう少し独立した運動環境として整えていただきたいなというふうに考えています。
学校の独自判断になっているのか、ちょっとその辺がよく分からなくて。学校の施設って結構多くのものが、自立性が強いような気がしていて、学校ごとに判断をしてしまっているような部分も結構あったりすると感じている中で、グラウンドの整備そのものについては、金額も少し大きくなりますし、頻度もきちんと管理をする必要があると思うので、できれば全体的な流れとして、これぐらいのタイミングでこういうふうに進めていくべきではないかということを、教育委員会から少し指導していただけないかなというところはちょっと希望があるのですが、御見解を伺いたいと思います。まずお願いいたします。 -
81:
◯教育長(竹内道則君) 校庭のマークの仕方については、現状のものの確認を、教育の担当の部署から担当の所管職員が行って確認をしております。それについての安全性はそういった形で確認しているところですが、くぎといいますか、金属製のものについての安全性も考慮した上で、プラスチック製のものに変えるなど、そういったことも含めて考えていきたいと思います。
それからグラウンドの整備については、予算の面もそうですし、実際に確認の部分についても専門性がありますので、こちらについては教育委員会の担当部局で全体を俯瞰して、計画的に判断してまいります。
以上です。 -
82:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。もちろん私たち学校教育以外で使わせていただいている団体も、学校の教育の妨げになったりとか、そういうことにつながらないように必ず気をつけていくので、全面的に協力して携わらせていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それから、ブルーキャップを先にやりたいと思います。やはりプロポーザル方式だったということで、技術面、内容の理解度であったり実績だったりという項目を御説明いただいたのですが、差し支えなければ、例えばどういう面に関する理解度が優れていたとか、それからどんな実績を持っている事業者なのかとか、やはり今回切り替わったことによって非常に期待感があるので、どんな評価を受けて、今回ここの新しい事業者が選定されたのかということについて、もう少し御説明いただければと思います。
また体制の強化ということで、先ほどの体制の強化というのは、人数を必要なところに少し増やして対応しているということを指していたのでしょうか。時間も少し延ばしているのですよね。ブルーキャップの時間帯も、夜遅い時間に少し延ばしたようなことも聞いていますので、もう一度その辺、今どんなふうに変化をさせて、今後どんな結果、いい形につながっていくのかということについて、御説明をお願いしたいと思います。 -
83:
◯市 長(松下玲子君) まず、事業者が今回替わったことで、その選定方法の中で、他の自治体でも実績がございます。当市よりも大きな繁華街を抱えているといいますか、何と言ったらいいのか、実績がございます。なので、視覚的にもユニフォームも変わりましたし、まだこの2か月間の実績ですけれども、これまで以上に、例えば路上喫煙者への指導などもかなり多くやっていただいております。
時間に関しては、変更前は、ブルーキャップパトロール活動時間は月曜日から金曜日、午後1時から午後11時までだったものが、変更後は、月曜日から土曜日で午後1時から翌午前零時まで行っています。また、これまでは土曜・日曜・祝祭日は午後4時から午後10時まででしたが、日曜・祝祭日のみ午後1時から午後10時30分までという形で、活動時間が増えています。
そうした中で活動時間延長に伴う活動量が増え、また、深夜・早朝時間帯の客引き行為等への対応は、この市の条例に基づく指導等を行う指導員を兼ねて、ミッドナイトパトロール隊運用を変更して行っておりますので、効果が出るような形になってほしいという思いで、様々工夫をしているところでございます。
以上です。 -
84:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。そうなのですね。大きなまちで実績があるということで、何か鍛えられている方がメンバーにすごく多くて、年齢もかなり若いなという印象があって、見た目もすごいです。たまたまちょっと交差点のところで会って話した方がすごく若い方だったのですけど、私がリーダーなのですと言って、名刺を頂いてお話も少しすることができました。
すごく一生懸命考えて取り組んでくれているなというのが伝わってきたので、これからどんどんその効果が上がっていくということに大変期待していますので、ちょっと前回の質疑の中で、どこを目標にしているのですかという、私が質問させていただいたことについて、完成のゴールをなかなかはっきりと示すことはできないのだけどという御答弁をいただいてはいますが、さはあれど、逆にゴールがないならば、常に追求し続けていただかなければいけないのではないかなというふうに考えていて、吉祥寺の南もそうですし、東のほうもそうですし、ぜひ広く面的にそういったことをやり続けていただきたい。大変期待しておりますので、どうぞよろしくお願いします。
それでは子どもの権利のほうに移りたいのですが、すみません、先ほど教育長は生徒指導提要とおっしゃったのか。言葉としては生徒指導要領ではなかったので、また別のものがあるのだなと。その御説明の中で、校則を決めるときのやり方について、こういうふうに新しく内容が変わったのですという御紹介をいただきました。その中で、生徒自身とのコミュニケーションを取ったり、それから、ごめんなさい、ちょっとそこを全部きちんと理解できなかったのですが、確認を取ったり、議論をしたりするというような御説明をいただいたと思っています。
それで、先ほど質問1の2の1)家庭におけるしつけ等について市長から御答弁いただいた、侵害するものではないですというふうに考えていらっしゃると。きちんと子どもの権利が守られるように、大人が心がけるというふうにおっしゃっていただいたのですが、その心がけることが難しいのではないかなと思っていて、それをどうやって心がけていくのか。それについてもう少し具体的に、こんなことをこれからやっていきたいというようなことがあれば、ぜひ伺いたいなと思っているのです。
ちょっと私の個人的な話であれなのですけど、親の心子知らず、子の心親知らずで、私は男児2人を育てて、もう2人とも就職しているのですが、下の次男坊は、私が今やっているサッカーのチームに所属していて、長男が始めたのをきっかけに、私もそこで一緒に指導をやったりしてきたのですけど、二十歳を超えたあるとき、その次男坊と一緒に、やっとお酒を飲むことができるようになって話をしていたら、もうびっくりなのです。俺、サッカー嫌いだったと言われてしまったのです。まさか、あんなに一生懸命に親子で毎週グラウンドに通って、子どもはもう大好きでサッカーを一生懸命やっているものだと思った。それが何年もの時を超えて暴露されてしまう、親のびっくり。
そのときに思ったのは、やはり親子のコミュニケーションってすごく大切で、もちろん子どもが小さいとき、私はやっているつもりだったのですけど、そもそも大体自分ができていると思っていたことが間違っていたのです。きちんとそこで親子の会話が成立していて、子どもの心に届いていたのだというふうに思って子育てをしてきた自分を、すごく強く反省しました。
今日の壇上の質問の中で述べさせていただいたのですが、小山先生の話のときに、何度もスキルという言葉を使わせていただいているのです。だから心がけるためには、もう一つ踏み込んで、大人がスキルを身につける必要があるのではないか。それは例えば一例として、アンガーマネジメント──これは手法です──であったり、コミュニケーションスキルであったり、そういったものが大切。それは簡単には身につかないと思うのです。なので、これからこの子どもの権利条例を実効、きちんとした効果あるものにしていくために、市としてはどんなことを考えていこうとしているのか。もし今ここにお考えがあれば、ぜひ伺っておきたいです。
これは、市が全部やることでしょうというふうに言うつもりは全くなくて、関わっている大人が全てそのことについて気づいて、そのことに真剣に取り組むことで初めて、いい結論に向けて動いてくれると信じているので、まずできれば市のほうからきっかけをつくっていただいて、市民が、この権利条例が制定されたことを機に、これからみんなで子どもの権利を、そして、ただ子どもの権利というよりも、人間同士の権利として守っていくことができる、そういう市になっていくことを考えていっていただきたいなと思っています。
そういう意味で、実効性を上げるために、心がけることからもう一歩踏み込んで、何か具体的に、これからこういうことをやってみたいなという思いがあったら、ぜひここで教えていただきたいと思います。お願いいたします。 -
85:
◯市 長(松下玲子君) 宮代議員から壇上でも御紹介いただきました青少協の委嘱状の交付式において、あそび庁の小山先生から、御講演というよりも、私もああいう形は初めてでしたので、単なる講演ではなくて、一緒に遊びの奥深さを学べる、とてもいい取組だったなというふうに思っています。
私はあの場にいて体験を通じて、やはり子どもの気持ちを分かったつもりになってはいけないなと。本当に子どもの気持ちになれるかというと、やはりかつての子どもだった自分としては、分からないことのほうが多く、でも一緒に声を出して動作をすることだったり、同時発声、同時動作の効果などの理論を学ぶ中で、すごく実体験に基づいた、研修のような取組だったなというふうに、私自身は思っています。
御質問の中の、おっしゃるような、子どもにとって何が一番いいか、子どもの最善の利益を第一に常に心がけていくということ、これは言葉で言うのは簡単ですけれども、それを大人が本当に実践していくのは、とても大変難しいことだという認識を私も持っています。実際に我が子と接していても、宮代議員がおっしゃるような、後になって分かったということもあるでしょうし、目の前にいる我が子が本当に本音で自分に話してくれているのかというところは、常に言葉だけではなくて、態度だったりとか、あとはどんな行動を取っているかというところで観察しなければいけないのかなとも思っています。
やはり子どもの権利条例がスタートしたことが、これから出発であり、様々な気づきだったり学びの場を市としても提供できるような、そして大人も子どもも、条例の思いや趣旨や、そして本質の部分を一人一人が理解できるような取組を、大変だと思いますが、こつこつと続けていって、理解を深めていきたいなというふうに思っています。 -
86:
◯教育長(竹内道則君) 先ほど御紹介したのは生徒指導提要といいますが、生活指導などを行う際の目安になるもので、今回の改訂は、たしかその中で明記されていたと思いますけれども、こども基本法の制定などが背景にありますので、そういった、言ってみればルールの見直しを定めていくに当たっても、子どもたちの関わりを求めていくということが規定されて書き込まれたものだと思っております。そういうふうに理解しております。
学校の先生は子どもと関わる専門家ですから、例えば宿泊の行事、セカンドスクールなどでも、それぞれ自分のこうあるべきだということを踏まえた上で、いろいろないさかいが起きる中で、どうしてそういう行動が出たのかということについても、子どもたちが時としてそれを表現できないときに、先生達は、なぜそういう行動になったのか、どうしてそうしたかったのかということを、丁寧に言葉として引き出そうとしたりしています。そういったことも含めて、御紹介があったアンガーマネジメントなども、学校の現場の中で取り組まれていたり、先生方が個々に取り組んだり、いろいろと身につけるように、それを発揮するようにされています。
そこを教育委員会として、一律にこれをこうしましょうというよりも、むしろ校長には、そういったことが必要だという背景を申し上げていますし、子どもの権利条例が制定されたということは、このプロセスも含めて学校は共有しているわけなので、それをどのように先生たちが理解して実効性あるものにしていくのかというのは、専門家集団であるだけに、目的を示せば、各学校で具体的に実施して、実現に向けて努めていかれると思いますので、私はまずその推移をよく見極めて、抽象的な言い方になると思いますけれども、必要であればさらに、こういうことはどうでしょうかというように努めていきたいと考えております。 -
87:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございました。最後の先生の話ですけど、私はやはり昭和育ちで、実は私は剣道部だったのですけど、剣道の先生がすごく怖くて、当然剣道部ですから常に竹刀を振り回しているわけですが、普通にたたかれていましたから。まだそういう時代の方たちも先生の中に。それもかなり権力──権力って変ですね。要するに、地位のあるところに、その昭和の時代に育った方がまだ教育者として残っている。こういう残っているとか失礼な言い方をしてはいけないかもしれないですけど、それは学べば少しずつは変わっていくのかもしれないのですが、もしかするとそういうしみついているものとかがあるのではないかなということを、ちょっと危惧したりしている。そういう側面の危惧もあるので、最後に教育長がおっしゃっていただいたとおり、きちんと目を光らせて、必要があることには御提案をいただくというようなこともおっしゃっていただいたので、そこはすごく大切なのではないかなと感じています。
それから生徒指導提要についてありがとうございました。特に今回議論をして校則を決めるのに、児童生徒も含めて議論していきましょうということを定めていくような、こんな気の利いたものがあるのだということで、非常にありがたいなというふうに思いましたので、私ももっと勉強しなければいけないなと思いました。そういったことをベースにして、これから築き上げていく必要があるのだなというふうに思っています。
それで、さっき市長におっしゃっていただいたように、あのワークショップ。私はワークショップと申し上げましたけど、講演会、いわゆる特別講演会ですけど、やはり実践はすごく大事で。ただやはり最初の御説明によると、学校で児童生徒へは、「こどものけんりってなぁに?」という紙を配っていますとか、それを見ることができますとか、先生自身は研修ですとか。研修はもしかすると少し双方向的なものとかも取り入れているのかもしれないのだけど。保護者へのアプローチもお便りですということになってしまっていて、そうなりがちだなとちょっと感じていて、それで伝わっていくのだというふうではない流れができつつあるのではないかなと思っている。
でも、先ほど市長は、これからいろいろなことをこつこつとやっていきたい、それからあとは理論も大切だとおっしゃっていただいたのは、私は非常にありがたいなというふうに思いました。やはりただ感性だけでやるのではなくて、様々な新しく学んでいる、小山先生のような方たちもいっぱいいらっしゃると思うので、そういった分野の方たちの力も取り入れて、武蔵野市の教育の行く方向を、子どもの権利を守るのと同時に取り組んでいただきたいということに、大きく期待しておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
すみません、ちょっと今日は勝手に長くしゃべり過ぎたのですが、もしというか、ぜひよろしければ、最後、コメントいただければと思います。
以上です。 -
88:
◯市 長(松下玲子君) 今年度、この4月からスタートいたしました子どもの権利条例について、まだまだ御存じない方もいらっしゃると思いますので、様々な手法を用いて、手を替え品を替え、あの手この手で知っていただいて、そして、子どもにとって何が一番いいかということをみんなで考えて、実践ができるような、子どもに優しいまちになるように、みんなで取り組んでいきたいと思いますので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
以上です。