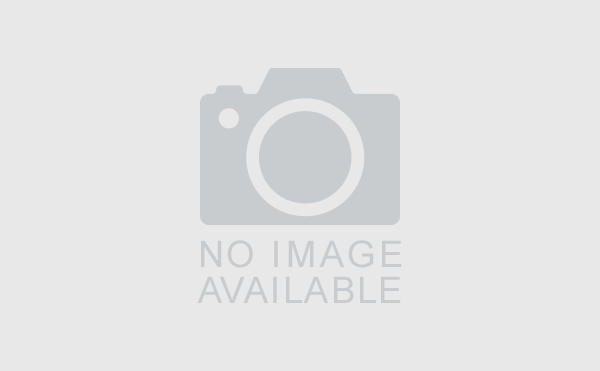令和6年第3回定例会 2024-09-05(録画中継と議事録抜粋)
- 令和6年第3回定例会 9月5日(木) 本会議 一般質問
未来につながる教育と児童生徒との合意形成について
・学校施設の利用について
・学校交流について
・「らしさ」について
・学校整備の今後について

- 議事録
◯6 番(宮代一利君) おはようございます。6番、ワクワクはたらく、宮代一利です。ここ数日、天気に恵まれて、今日も気持ちのよい晴天になりました。この夏、ゲリラ豪雨に雷に恐ろしい夜を、あるいは朝方にも雷が鳴ったりして、非常に気候に悩まされたということが記憶にあります。
この夏は、南町カーニバルから私は始まりました。南町カーニバルというのは子どもたちに楽しんでもらう夏祭りで、地元住民が実行委員会を編成し、南コミセンの協賛をいただき運営する夏祭りです。一夏を過ごした今でこそ、今申し上げたゲリラ豪雨や雷には、大分慣れっこになってきたような感覚はしますが、7月の3週目の土日の開催で、まだ雷、ゲリラ豪雨に慣れていない状態でした。初日は大変暑い日でした。小美濃市長にも御来場いただきましてありがとうございました。
その日の最後のプログラムで盆踊りがありました。盆踊りが始まって2曲目を踊っていたそのとき、いきなり大粒の雨がぼつぼつと降ってきました。そして遠くで雷が聞こえたかと思った途端、突然大きな音で雷が襲ってきたのです。ゴロゴロというかわいらしい雷ではなく、バリバリ、ドドーンという、もう振動が伝わってくるような物すごい音がしました。多分すぐ近くに雷が落ちたのだと思います。盆踊りはもちろん中断して、校舎の中や体育館に一時避難をしました。校長先生が待機してくれていて、教室と体育館に退避することを臨機応変に許可していただきました。大変感謝しています。
1時間ほど避難しましたが、もうグラウンドは水浸しで、全然元に戻れるような状況ではありませんでした。まだ小雨が残っている状態でしたが、子どもたちも御家族の皆様も、無事に帰宅することができたのではないかと思います。けがをしたというような連絡はなかったので、皆さん無事だったというふうに思っております。
2日目の夜には花火大会を開催することができました。この日はゲリラ豪雨もなく、雷もなく、無事に開催できました。大勢の近隣の皆様、子どもたちにお集まりいただき、花火が打ち上がるごとに、おおという歓声が上がり、とてもうれしい時間になりました。
まず最初の質問です。学校施設の利用に関する確認と考え方について整理していきたいと思います。1番、学校施設の利用について。
質問1の1、現在の運用の原則について伺います。学校教育を最優先に考えるのは当然のことで、平日の授業があるときは、基本的に学校に入ることは禁止されていると理解しています。運動会、文化祭といった行事の際は、地域の方が入場することは許可されていると思います。また、PTAや地域の方が学校に用事があるときは、事務室を通り校内に入るなど、現在どのような運用になっているのか、まず原則について伺いたいと思います。
また、地域との関わりとして、学校施設を利用するケースで、例えば学校施設開放のような場合、事前申請をして許可を得て入るなど、やはりこちらについても運用の状況について伺います。
質問の1の2です。複合化に関する検討の進捗状況について。学校改築の基本計画の段階で複合化に関する議論がありましたが、その議論は終結していないと認識しています。既に改築に着手している学校がありますが、時代の流れの中で考え方も変化しますので、今後も複合化の議論は継続していくものと思います。公立の学校ですから標準化は求められる部分も多くあると考える一方で、既に改築が進んでいる学校と全て同じものを造るという発想に縛られないで、時間の経過とともに柔軟に考える必要があると感じています。学校施設の複合化に関する検討の進捗状況と今後の考え方について伺います。
質問1の3、グラウンドの整備について。
1)ペグの露出などの危険を取り除くための市内学校のグラウンド整備の進捗状況について伺います。
2)令和5年第2回定例会の一般質問において、グラウンド整備の件を質疑しました。その際教育長より、グラウンドの整備については実際に確認の部分についても専門性がありますので、こちらについては教育委員会の担当部局で全体を俯瞰して、計画的に判断してまいりますとの答弁をいただいております。各学校における整備状況の現状について把握しているのか伺います。
冒頭のカーニバルのお話の中でも触れましたが、最近はゲリラ豪雨などに襲われることも多くなり、グラウンドも水浸しになることがあります。雨水浸透貯留槽を整備していただいているおかげで、水はけがかなりよくなっていると感じています。それでも表面の土が洗い流されており、くぎ以外の突起物が出ている例もあります。こういった状況を把握しているのか、どんなルールで把握しているか、御説明をお願いいたします。
3)様々な要因でグラウンドの劣化は進みます。計画的整備が必要と考えますが、今後の取組に関する考え方を伺います。
大きな2番です。学校交流について。
昨日も多くの議員からこの議論がありましたが、8月18日に武蔵野市議会始まって初めての子ども議会を開催しました。市内中学校の生徒14名に子ども議員となっていただき、6つの中学校ごとに自分たちの思いをプレゼンテーションしていただく、そしてそれに対して私たち議員が答弁をするというイベントでした。その中で中学生たちが望んでいることを様々聞くことができました。どの指摘、要望とも、とてもすばらしいものだと感じました。その中から、今日は学校のイベントに関することを取り上げたいと思います。大きく言えば、生徒たちは他校との交流を望んでいるということです。
1つ目のアイデアは、既に学校で行われているイベントを他の学校の生徒が見学に行く形で交流することができないかというものでした。そのことについては、現状の学校施設の運用においては様々な難しさがあるのかなというふうに感じています。将来的には、それも乗り越えることができればというふうに考えています。
2つ目のアイデアは、学校施設ではなく公共施設、例えば陸上競技場であったり、総合体育館であったり、そういったところを使って、複数の学校が同時にイベントを開催するというものでした。全校合同運動会や合同大文化祭を開催するというイメージです。
今回の子ども議会の中で、私が非常に衝撃を受けた話がございます。それは複数の学校のプレゼンの中で、夢物語という言葉が出てきたということです。自分たちがこういうことをやりたい、こんなアイデアがあるということをプレゼンテーションしながら、でも自分たちは、これは夢物語であるということは分かっているのですというふうに表現するのです。
平たく言ってしまえば、どうせ駄目に決まっている、大人はきっと何かの理由をつけて、こういったアイデアを受け入れてはくれないというふうに感じているということです。それを前提として考えているということが分かりました。それでも、今回は駄目元で言うだけ言ってみよう。市長さん、議員の皆さん、自分たちの考えや気持ちに耳を傾け、実現してくれませんかと訴えていました。もしかしたら多くの生徒たちはふだんから、思いを口にしないというのが当たり前になっているのかもしれません。
質問2の1、学校施設における交流について。生徒が希望する場合、運動会、文化祭など、既に開催している行事を他校の生徒が見学をすることはできるか伺います。
質問2の2、学校施設以外における交流について。総合体育館、陸上競技場などの公共施設を活用して、複数の学校が合同で運動会、文化祭などを開催することについて、考えを伺います。
質問2の3、児童生徒と学校の合意形成について。児童生徒の希望、意見をいかに聞くか、現在行われていることについて伺います。今後こういった児童生徒の希望、意見に耳を傾ける、さらに実現するために取り組もうとしていることについて伺います。まず意見を聞き、コミュニケーションを取り、子どもと大人の考え方のずれを明確にし、歩み寄り、合意形成する。こういったことが求められていると考えますが、いかがでしょうか。
大きな3番です。「らしさ」について。「らしさ」ということについて考えてみたいと思います。まず市長は、武蔵野市らしいとはどういったことだというふうにお考えか伺います。
質問3の1、武蔵野市らしさについて。武蔵野市の特徴、武蔵野市らしさとは何かについて伺います。今回一般質問で「らしさ」というものを取り上げる中で、まず自分らしさって何なのかなということを考えました。何か自分らしさというものはあるとは思っているのですが、それを言語化して表現しようとすると、なかなか難しい。そして、それほど厳密に定義できるものでもないのかな、空気感というか、雰囲気のような要素も多分にあるのではないかなというふうに感じています。
ここで、学校の特徴ということについて考えてみたいと思います。公立学校は公立であるがゆえに、標準化、あるいは公平性といったものが求められる部分が多くあるのではないかと感じています。一方で、それぞれの学校において特徴的なものを出す、○○学校の「らしさ」というものを打ち出していこうというような考えもあるのではないかと思います。
一例ですが、私は杉並区立宮前中学校の卒業生です。以前、校庭のくぎの事件のときに、卒業生であるということをお話ししました。当時の宮中、宮前中学校の音楽の授業は大変特徴的でした。小林光雄先生という音楽の先生がいらっしゃって、杉並混声合唱団の創始者であり、現在もこの合唱団は盛んに活動しております。小林光雄先生は既に他界をしております。この小林先生の音楽の授業は、3年間合唱しかやりません。合唱のみをやるという、学習指導要領において認められることなのだろうかと、今さらながら疑問に感じるところもございます。
1年生の最初の授業で、授業のやり方について先生から説明があります。中学生ですからピアノを弾ける生徒はクラスに何人かはいるもので、クラスのピアノ担当が複数選出されます。そして指揮者も何となく決まっていって、そうすると先生は音楽室からいなくなります。与えられた課題曲を自分たちで練習に取りかかります。最初は面食らうわけですが、だんだんとできるようになるのです。そして1学年が終わる頃、年度末に合唱祭があって、そこでクラスごとに披露し、採点もあり、順位が決まります。3年生は3回目ですから、年度の初めから真剣勝負です。もう既に流れが分かっていますから、自分たちで1年間のストーリーを組みながら取り組みます。さらにその先には合唱部というものが存在していて、この合唱部が毎年全国大会にまで出場するという常連校になっていました。
非常に極端な例ではあるかと思いますが、宮前中学校といえば合唱、これは一つの大きな特徴だったと感じています。おかげで私は今でも音楽は大好きです。自分という人間の一部を形づくっていると思っています。とても感謝しています。こういった非常に特化した特徴というものは、現にあるのかもしれません。武蔵野市においても吹奏楽が盛んで、それを中心に活発に活動しているという場面もあります。ほかにも様々学校には特徴があると思います。今後も生徒たちが楽しい、行きたい学校であることを求めて、特徴ある学校づくりに取り組むことが大切なのではないかというふうに感じています。
質問3の2、武蔵野市が目指す教育について。武蔵野市らしい教育とはどのような教育か、目指す方向性について伺います。
質問3の3、公立学校の特徴について。特徴ある公立学校を目指すことについて伺います。先ほど申し上げたように、公立学校は均質性や平等な機会の提供などを求められる側面があると考えています。これを担保しながらどんな特徴を持つことができるのか、考え方を伺います。
大きな4番です。学校整備の今後について。
第六期長期計画・第二次調整計画策定において、今後の学校改築の在り方の検討という項目が挙がっています。市内公立学校の統廃合についてということがテーマの一つに取り上げられています。これは、物理的な改築、建設等に関する合理性、合理的な方法を考えたときのアイデアとして統廃合ということが出てきて、その考えるプロセスが適切でなかった部分があったのではないかというふうに感じています。統廃合するか、しないかという前に、まず武蔵野市の教育の在り方について考える必要がある。そしてこれは継続的に考え続けるものであり、ゴールがあるものではないというふうにも感じます。
学校施設の整備、改築には、様々な要因が関係していると考えます。将来の児童生徒の数であるとか、教育の方法、例えば1人に1台のタブレットを配っていますが、これからはこれを活用したオンライン授業といったものも可能性としてはあるのかなと思います。そういった前提条件が変化する、その前提条件の変化に対応しながら、学校施設について検討を継続する必要があるというふうに考えます。
本日、学校の複合化についても議論させていただいています。地域に開かれた学校の在り方もまた、大切な要素と考えます。既に2校が改築に着手し、さらに今後も計画的に継続的に学校改築が進んでいきます。公立学校に求められる均質性、あるいは平等性といったものを担保しつつ、それぞれの学校が特徴を出していく必要があると思います。最初の改築をやってしまったので、もうその方式を取るしかないというふうにとらわれてしまうことなく、まず学校教育に対する考え方の構築、地域との親和性も含めた面的な学校の配置の検討、そういったことを継続的に検討しながら、その中の一つの選択肢として統廃合というものも浮上してくるかもしれない。そういった流れの中で今後考えていただきたいと考えます。
質問4の1、学校選択制について。
1)なぜ学区域を設定しているのか、その理由について伺います。恐らく歴史的な背景があると想像できますが、根拠となっているルールがあるのか、学区域の見直しが行われたことはあるのか、考え方について伺います。
2)学校選択制の導入について伺います。学校選択制についてはメリット、デメリットがあります。全国的に議論があるようです。この学校選択制に対する武蔵野市としての考え方について伺います。
質問4の2、選ばれる公立学校について。学区域をなくした場合、学校ごとに希望者の人数がばらつく可能性が考えられます。この可能性を受け入れながら運用する方策について考え方を伺います。今回、「らしさ」について議論させていただいています。各学校の「らしさ」を打ち出し、魅力ある学校づくりを展開し、この学校に行きたいと選ばれる公立学校になることは大切なことだと考えます。
先日、市内中学校の卒業生と話をするチャンスがありました。アラサーの若者で、市内で元気に働いています。その方のお話によると、自分はある市内の中学校で合唱部に入りたくて、学区外からその中学に行きましたと、にやりとしながら語ってくれました。どんな手を使って越境したのかは謎です。しかし行きたい学校があり、そこを選ぶ。そんなことが市内でも起こっているようです。人数がばらつくことをリスクと捉えるばかりでなく、むしろそれを根拠に統廃合の議論に結びつけることもできると考えています。通学距離など物理的な側面も学校の特徴と言えると思います。そういったことも含めて、実態を分析することができると考えます。
質問4の3、統廃合に関する議論について。以上述べてきたとおり、未来の教育を設計する中で、学校施設の配置についても検討が進むものと考えています。総合的な議論を行うことについての考え方を伺います。
以上、壇上からの質問といたします。よろしく御答弁をお願いいたします。 -
3:
◯市 長(小美濃安弘君) 宮代一利議員の一般質問にお答えをいたします。
私からは、大きな3番目の「らしさ」、武蔵野市らしさについてお答えをさせていただきたいと思います。大変抽象度の高い質問だなというふうに感じておりますので、まずこの場でお答えさせていただいて、もし答弁が足りなければ再質問いただければなというふうに思っております。
例えばソフトとハードと分けた場合、ハード面から言うと、これは今回私も初めて市長に就任して、来年度武蔵野市に入庁するための面接を、初めてやらせていただきました。ほとんど学生の皆さんなのですけど、中には中途から入っていらっしゃる方もいらっしゃいます。ただその中でも、多くの方が口にするのが、武蔵野市らしさって何ですかということを質問すると、緑多いまちが好きです、好みですと、こういうふうに返ってきます。私もそうだと思っています。
やはり11平方キロメートル、あまり大きな市の面積ではない中で、なぜ緑がこんなに多く感じられるのかというのは、長年用途地域が、今は第一種低層住居専用地域と言いますが、昔は第一種住居専用地域と言いましたが、いわゆる建蔽率40%、容積率80%のエリアが非常に多いため、屋敷林を含めた緑がすごく多い。11平方キロメートルの中に約14万人が住んでいるのにもかかわらず。人口密度としたら、これはすごく高い数字です。しかしその中でも、空地には緑が植えられ、また武蔵野市には緑の憲章もございます。そういった中で緑を大切にしてきた。こういったことがハード面では、大変私も武蔵野らしさではないかなというふうに思っています。
ソフト面ではどういうことかといいますと、ソフト面では、これもいろいろなところで書いてありますが、やはり市民参加、市民自治のまちであるということではないかなというふうに思っています。これはもう宮代議員も様々なところで市民参加を、御自身もなされていたし、今議員という立場で、様々な場面で市民参加の取組を御覧になっているのではないかと思うのですが、他の市でもそうなのかもしれませんが、私は武蔵野市は、特にという言い方はひょっとして正しくないかもしれませんけれども、非常に市民参加に対する意識が高いまちだと思っております。
なので、今ここでお答えできるのは、ハード面では大変緑の多い地域であるということ。ソフト面では、市民参加による、市民と一体となって今までも市政を進めてきた。そしてこれからも市政を進めていく。これが武蔵野市の「らしさ」ではないかなというふうに思っております。
他の質問に関しましては、教育部長より御答弁をいたします。 -
4:
◯教育部長(真柳雄飛君) では、私から残りの質問ということになります。
まず、大きな1番の学校施設の利用の1の1のところです。学校施設開放の運用の原則のところの御質問です。地域活動の学校施設の利用につきましては、武蔵野市立学校施設の開放に関する条例により、利用できる施設や料金、学校教育に関する時間を除いて、市民に使用させることができる旨を規定しております。学校教育に使用する具体的な事例としては、運動会や部活動などの準備行為を含む使用期間が挙げられますが、この期間は地域活動の使用に開放はしておりません。
施設の利用を希望される場合は、要件として、まず構成員が10名以上であることだとか、市内の在住、在勤、在学者が2分の1以上いることだとか、代表が成人であること、会費を徴収している団体においては会計内容が明らかになっていることなどの要件を満たしていただき、構成員名簿などを添えて団体登録をしていただく。そういった手続を踏んでいただいているということでございます。
1の2、学校施設の複合化に関する検討の進捗についての御質問ですけれども、学校施設の複合化については、第2期公共施設等総合管理計画において一定の整理を行っているところでございます。第一中学校、第五中学校については、生徒数が増加傾向にあるため複合化は実施をしないと。また、第五小学校、井之頭小学校についても、児童数が増加傾向にあることに併せて、校地が狭小で敷地に余裕がないことから、複合化は実施しないということでございます。ただし、将来児童数の減少により施設的に余裕が発生した際に、スケルトン・インフィルの設計を取り入れておりますので、ハード面での複合化の対応が可能というふうに考えております。
次に1の3のグラウンドの整備のところで、まず1番目、市内の学校のグラウンドの整備状況についての御質問ですが、各学校が日常的に点検やメンテナンスを行いながら使用していただいております。教育委員会では昨年度、第四小学校、大野田小学校、今年度は第四中学校、関前南小学校の校庭の改修を行っております。
2番目の各学校における整備状況について把握しているかとの御質問でございますけれども、校庭は天候や使用頻度などにより日々状態が変化しております。各学校でその状態を把握しながら使用しております。水たまりができやすくなっただとか、状態が悪くなった場合は、学校から教育委員会に連絡をいただきまして、現場を確認した上で必要な助言や対応を行っているところでございます。
3番目の計画的な整備についての考え方の御質問ですが、従来、雨水貯留浸透施設の設置に合わせて、計画的に校庭の整備を行ってまいりました。校庭の状態は、日当たりや使用頻度などにも大きく影響を受けます。今年度から専門業者による点検を行うこととしたことから、その点検結果も参考としながら、必要な整備を行っていきたいと考えております。
次に大きな2番です。学校交流のところ。
まず2の1、他校の生徒が見学することができるかについてでございますけれども、こちらは他の議員にもお答えしたとおり、これまでの事例を見ますと、生徒同士のトラブルにつながった例もあるということで、また防犯の観点からも、学校側においては慎重に判断しているということかと思います。
次に2の2、複数の学校が合同で運動会、文化祭などを開催することについてですが、こちらも他の議員にお答えをしておりますけれども、市の教育委員会では様々開催をしております。このことで文化、芸術、運動を通した学校間の交流を図ってはおりますが、今後の展開については、市主催の行事も含めて考えてみたいというふうに思っております。
次に2の3、児童生徒の希望、意見を聞くために現在行われていることについてお答えをいたします。例えば昨年度、1月のむさしの教育フォーラムでも報告をいたしましたが、展覧会実施方法について子どもたちが一から話合いを進め、自分たちの手で学校行事をつくり上げた事例がございます。ほかにも学校の決まりの見直しや運動会の実施種目について、実行委員会の子どもが話し合い、全校の子どもたちや保護者に発信しているといった事例もございます。
こうした児童生徒の意見表明は、令和4年12月に改訂された生徒指導提要でも、生徒指導上、理解しておくことが不可欠なものと示されており、本市においても武蔵野市子どもの権利条例で、意見を言い、参加する権利を規定しております。市教育委員会としましても、令和6年度の基本方針の中で示しており、現在、各学校の実態に応じて、児童生徒の希望、意見を反映する教育活動を充実させているところでございます。
次に3の2、武蔵野市らしい教育、目指す方向性についての御質問ですが、武蔵野市教育委員会では教育目標を定めており、子どもたちが自らの人生を切り拓き、多様な他者と協働して、よりよい未来の創り手となる力を育むことを目標に掲げて教育を進めております。そういったものを実際に具体的にやって実現しているものが、例えば本市の独自の取組として、セカンドスクールであったり、武蔵野市民科であったりといった特色を挙げることができます。そういったものが武蔵野らしさの表れであるというふうに考えております。
次に3の3、公立学校の特徴についてお答えいたします。公立学校の均質性や平等の機会の提供、すなわち共通して取り組む観点としては、各教科等の学習内容について、学習指導要領に準拠していることが求められております。これは教育の水準の確保、教育の中立性において重要だと考えております。
一方で同じく学習指導要領では、社会に開かれた教育課程の実現が求められており、ここで学校ごとの特徴を打ち出すことができます。そうした取組を進める中で、例えば第五小学校、「元気」「本気」「根気」や、第三中学校、「責任ある自由」といった教育目標が、その学校らしさとして形づくられていくと考えます。
次に大きな4番、学校整備の今後についてでございます。
4の1の1)、2)は学区域のことで関連しますので、一括でお答えをします。市は、市内の学齢児童生徒を就学させるのに必要な小学校及び中学校を設置する義務を負っております。人数や通学時間、距離、規模などを十分に勘案し、必要な小・中学校を設置しております。本市では、学校、保護者、地域が一体となった教育環境づくりを進めるとともに、各校の児童生徒数をできる限り正確に予測して、必要な教室数を準備し、義務教育の適正実施のため、学区域を設定しております。そのため現時点においては、学校選択制の導入や学区域をなくすことは検討しておりません。
大きな4番の3番目の統廃合に関する議論についての御質問でございます。第六期長期計画・第二次調整計画の策定委員会で、全市的な視点で中学校の適正な数や校舎の在り方をどう考えていくべきかという視点で議論をいただく予定になっております。現段階ではその議論をしっかり注視しながら、今後の学校施設整備基本計画の改定につなげていきたいと考えております。
以上になります。 -
5:
◯6 番(宮代一利君) 答弁ありがとうございました。まず「らしさ」について、市長から御答弁いただきました。確かにソフトとハードというふうに整理していただくと、すごく分かりやすくなるなと思いました。その中でハードについては、やはり緑の憲章等をつくって、それを根拠に進めてきていると。それからもう一つ、ソフト面では市民参加ということで、やはり根源はコミュニティ構想が始まりだったと思うのですけれども、両方とも入り口の部分で、やはり誰かが引っ張っているように私は感じるのです。
コミュニティ構想も、さすがに一番最初の入り口のところから、市民がわーっと集まってきて、みんなでコミュニティを考えようというよりも、誰かそこに中心的な人物がいて、その方が引っ張って、そこでだんだんとその力が強くなってきたのかなというふうに。特にコミュニティ構想については、中心になっている人たちがちょっと目に浮かぶぐらい鮮明に理解していて、それから、緑の憲章をつくったときのそのいきさつについて、私はちょっと理解ができていないのですけれども、どんなふうにそれが引っ張っていかれたのか。
いずれにしてもその今出てきた2つの事例について、どういう方向性で、どういうプロセスでここに至ってきているのか。結局そういう流れができると、継続的に取り組むことができるようになる。そうすると、今後、ではどうするのですかと。今後も武蔵野市は今までの流れの中にいればそれでいいのか。さらに今は時代が変化しているのだ、時代の変化は大きくなっていますよねというときに、どういう方向に進んでいこうとするのか。それは誰がどんなふうに考えていくのか。そういった辺りについて、市長としてぜひお考えを伺いたいと思います。 -
6:
◯市 長(小美濃安弘君) 難しい質問だなというふうに思います。ただ、歴史的にどういう形で緑の憲章が制定されたのかとか、コミュニティ構想ができたのかというのは、ちょっと私はそのときにはいませんでしたので、コミュニティ構想はたしか昭和46年ということは、私がまだ9歳ぐらいの頃なので、まだ知る由もないわけであります。憲章がその2年後、48年ですから11歳。まだよく分からない頃で、歴史的背景はよく分かりませんが、ただ、そのときにやはり課題というか、そういった何らかの背景があり、コミュニティ構想ができ、その2年後に緑の憲章ができたというのは、当時としてはそれなりの意義があったのだろうなというふうに思います。
ただ、それがあるから、それに引っ張られて、今市民の方々が、住民自治もしくは市民参加をしているのかというと、それは少し違うかなというふうに思います。そういうことを知らずに引っ越してきた方もたくさんいらっしゃいますし、そういうことを知らずに育った市民の方もたくさんいると思います。ただ、そういった土壌があって、風土があって、まちの雰囲気というか、空気感があったというのは、当然あったのだろうなというふうに思いますが。
例えば市民参加とか住民自治とかと、1つだけ例を申し上げますと、私は平成17年から23年の3月まで浪人生活をしておりましたので、一般市民でおりました。そのときに、ちょうど今も少し問題になっておりますけれども、法政高校跡地問題というのがありまして、法政高校のあった場所が移転して、そこにマンションデベロッパーがすごく高い建物を建てるということがありまして、住民運動が起きました。その住民運動に一市民として参加させていただいて、非常に勉強させていただいた思いがございます。
そのとき感じたのが、本当に一般の、今までは普通の主婦としてお付き合いをしていた方、また、会えば挨拶ぐらいはする近隣の方々が、自分たちのまちにこんな高い建物が建つのはやはり問題だということで、立ち上がって、運動を始めたのです。これは別にコミュニティ構想があったからではなくて、やはり自分たちのまちは自分たちで守るのだと、そういう意識、住民自治、市民自治の考えから出てきたのだと思っています。私もそう思いました。非常に理不尽な話でした。
先ほど用途地域の話をしましたが、用途地域の始まりは昭和35年です。もともと法政のあった場所というのは、帝国美術大学、武蔵野美大の前のところは、もともと大学があったのです。なので、大学は実は第一種住専には建てられませんので、もともとそこに大学があったがゆえに、その地域だけは第一種住専から外れていたと、そういう地域でありました。なので高い建物が建てられたのです。周りは全部第一種住専だったのですけれども、そこだけ高い建物が建てられたと。ただ、美大も法政も、第三中学校までエリアだったのですが、15メートルに抑えられていたのです。
だから15メートルまでは住民として許せるということで、15メートルの地区計画を自分たちでつくってしまったのです。自分たちでつくって、それを市に提出する。すごいことです。ふだんは行政や議会に自分たちの生活やまちづくりを負託しているわけですが、いざ危機が迫ると、立ち上がり、自分たちでまちのルールまでつくってしまうという、この市民参加、市民自治の力に、私は平成7年から市議会をやって、13年から都議会議員もやっていましたけれども、じかに住民の力を見せつけられたという感じがありまして、すごい力だという思いを今でも持っています。
それが、市に提出したものは結局却下され、市が独自に地区計画をつくったのですが、しかし15メートルのエリアというのは採用していただいたので、今問題になっている、今回建設委員会にも陳情が出るようでございますが、そのマンション計画も、15メートルの範囲で抑えられているわけです。あのときの運動は、少なくとも高さだけは抑えられたということで、住民の力でまちのルールをも変えることができる、そういう思いを持っております。
ですので、決して従前にあった条例とか従前にあった計画とか構想、こういったものに引っ張られて住民は動いているのではなくて、武蔵野市──武蔵野市と言ってしまうとどうか分かりませんけれども、少なくとも市民の力というのはそういうものを持っている。またそういうことで、様々な武蔵野市の市政が進められてきたのだろうなというふうに感じているところであります。ちょっとお答えになっているか分かりませんが、もしあったらまた再質問してください。 -
7:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。確かに何か大きな、言わば問題というか、そういうのが出てくると、それに対しては物すごい結束力を持つというのはよく理解できますが、別に問題がないときでも、言葉が難しいけど、この後会派として担い手不足の議論をしますけど、担い手不足って、私は先ほど御紹介していただいたとおり、地元で様々活動を今までやってきていて、担い手になろうと思ってやったことはないです。
言ってしまえば、入り口は巻き込まれるのです。周りにいる仲間が私を巻き込んでいって、そうすると、いつしかもう楽しくてしようがなくなる。それでもう抜けられなくなる、そういう形で。結局私も後から武蔵野市民になっているので、武蔵野市らしい市民、武蔵野市民らしい人間につくられていった、地域によって自分がつくられていったなという印象を持っていて、今後もそんなことが続いていくのかなというふうには思っています。なので、そういったことを大切にしていくことを、これからも考えていきたいなというふうに思っています。答弁ありがとうございました。
さて、教育のほうにちょっと移らせていただきます。まず、一番最初の質問1の1のところ、ちょっと私の質問が十分でなくて、学校開放のことだけではなくて、そもそも学校のルールというか、人が入れないとか。当たり前ですけれども、授業中に校地に入ることはできないのかな。どんなルールになっていますか。まずそこの、根本的にそこに入れないようにしているルールはどんなふうにつくられているのかということについて、教えていただきたいと思います。 -
8:
◯教育部長(真柳雄飛君) 当然何か用事があって来るという方はいらっしゃいますので、受付を通っていただくということはあろうかと思います。何もなくてただふらっと入るとか、学校はそういう場所ではありませんので、通常は施錠がされていてというところはあるのですが、もうあらかじめ来場があるとかと分かっていることもありますので、その場合には受付にもその情報が入っていますので、そこで受付を通って学校の中に入っていただくという、そういう運用でお願いをしております。
-
9:
◯6 番(宮代一利君) そうだと思います。それの根拠はやはり池田小の話とかもあって、事件があって、そのときにさらに強化されたとかということもあると思うのですけど、結局リスクがそこにあるのだと。学校関係者以外の人間が入ってくることには、何か次のリスクにつながっているのですという考え方が根底にあるような気がするのです。先ほどのイベントの話についても、生徒同士のトラブルが考えられるからということを御説明されているわけです。
しかし、それが理由で学校を使った交流というのができないですという説明は、昨日の大野議員の議論のときもありましたけど、できない理由をただ述べているだけであって、どうしたらできるようになるのですかということを考えていきたいなと私は思っていて、なので聞いたのです。質問の1の1で、どういうルールになっていて、そのルールのどこを変えればお互いに交流ができるようになるのですか。トラブルをなくすためには、何をすればその交流ができるようになるのですかということを考えていただけないでしょうか。
まだ入り口に入れていないです、この議論は。まず門前払いで、今のルールがあって、それにのっとって考えるとできないのですと説明を受けているだけで。その説明で構わないのですけど。なので、もう一歩私は踏み込みたいと思っているので、このことを聞いています。今後前向きに考えていただけるのかということ。
ただ、他の施設を使ったものについてはこれから考えていきますと、昨日も前向きに御説明いただいたので、このことについては大変感謝しております。その提案した生徒たちも、えっ、こんなことを聞いてもらえるのだと、本当にそう感じていると思うので、私は担当した第三中学校の参加した生徒に報告に行こうと思います。議会でこんなふうに取り上げられていて、前向きに答弁をもらえたということを言いに行こうと思っているので。その次の一歩として、学校施設の今あるイベントにおける交流について、今後何かを変えていこうとしようとしてもらえないのか、そのことについて見解を伺いたいです。 -
10:
◯教育部長(真柳雄飛君) ほかの議員からもいただいている御質問でございます。まず基本は、学校の裁量というところがあります。前提としてできない理由というよりも、できるようにするにはというのは、それはそのとおりだと思っております。
学校側で、先ほど来トラブルというような話をしておりますのは、例えば運動会だとか、他の学校の子どもが来ることについて慎重な判断というのが、実際に例えば、誰かかっこいい子でもいいです、かわいい子でもいいのですけど、そういう子の写真を撮ってSNSで上げてしまうだとかそういうことが、恐らく校長先生になるまでにはいろいろな経験をされてその立場にいるということで、いろいろなリスクをやはり考えてしまうのだと思うのです。先生として、管理者、学校の責任を負っている立場としてはということなのだと思います。
やはり裁量という中に、責任があるところには判断する権限も当然そこはなければおかしいわけですから、こちらとしても、そういう意見があった、だからぜひ前向きに考えてほしいということを伝えていきますけれども、あまり圧をかけるというのですか、やってくれというのも、そこもまた学校の立場から考えると、いろいろ思うこと、考えること、リスクとかがあるでしょうから、そこはもう少し時間をかけて議論したほうがいいのではないかなと。あまり教育委員会としてぐいぐいというところは、ちょっとやはりどうなのかなというふうに思っております。 -
11:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。そのとおりだと思います。特にその管理をされている校長先生、副校長先生はじめ皆さん、まずリスクを考えて。ふだん私はリスクマネジメントをやりましょうと言っている立場ですから、当然出てくるし、不安もいっぱいあるだろうし、そう思います。
すみません、こういう質疑になると、私が圧をかけていて、圧をかけてくれと言っているみたいになってしまうかもしれないのですけど、決してそうではなくて、でも今部長からいただいた答弁の中で一番最後に、私はありがたいなと思ったのは、長い時間をかけてでもこのことについては考えていきたいとおっしゃっていただいたことが、まず入り口の扉を開けることができたのかなというふうに、今感じました。
ぜひ継続していただきたいし、逆に言えば我々も、むしろ生徒たちも言い続けると思います。言えばこういうふうに少しずつ伝わっていくのだという可能性を今回見ていると思うので、また言いに行こうといって。次回から子ども議会の参加者が増えるのではないかなということを期待しているような答弁をいただけたので、本当にありがたいと思います。ぜひ教育委員会のほうで、それから教育部のほうでも協力をして取り組んでいき続けていただきたい。そして不安を感じている校長先生はじめ、先生たちの不安を少しでも和らげるようなことをやっていっていただきたい。自由に学校らしい学校をつくるふうに、校長先生はじめ先生たちが取り組めるような、そういう流れにしていただきたいなということを希望いたします。
それから、ちょっと個別になってしまいますが、グラウンドの整備についてですけど、先ほどの御説明だと、やはりかなり学校の自主性というか、もうほぼ学校に任せているなという感じがします。実は先ほど名前が挙がらなかった、名前というか、御紹介いただけなかった。いただいたのは改修工事をやりましたという事例をばばばっと並べていただいたのですけど、8月の後半に本宿小学校でグラウンドのくぎ拾いをやっています。学校から声がかかって、利用団体が呼ばれて、利用団体は昨日の話のようにボランタリーに、全然報酬をもらわずに、50名ほどの人間が集まりました。グラウンドをずっとこうやって調べていって、くぎを1本ずつ拾ったということをしております。これは立派な整備だと思うのです。こういったことの報告はまず上がっていたのか。
私が先ほど申し上げた、どんなルールで把握しているのですかというのはそういう意味です。どこまで教育委員会が関わっていて、これは印象ですけど、今の印象だと、学校に任せきりかなと少し感じているところがあって、もう少し全体感として、自分のところはこういうことをしているのですとか、こういうことが問題なのですというところを、共有していく必要があるのではないかなと。
例えば先ほどゲリラ豪雨の話をしましたけれども、あれも実際に私は自分の目で、グラウンドの中に突起物が出てきていることを確認しているのです。これは運動する環境ではないなというふうに思っています。これは育成団体が埋めたペグとは違います。学校が運動会で必要としているタイルを埋めて目印をつくっているのですけど、もうそのタイルが浮いているのです。数ミリ浮いているのです。これを知っているのかというのが私は実は聞きたかったこと。どういうふうに把握していますかという、質問1の3の2)です。このどういうふうに把握というのは、前回の教育長の話で、専門性のあることなので、関係部局で取り組みますと話をいただいている。そのことが今どういうふうに進んでいますかということを質問しています。もう一度これにお答えいただきたいと思います。 -
12:
◯教育部長(真柳雄飛君) まず、本宿小という具体的なお名前が出ましたけれども、それでそういうボランタリーという言葉でありましたけど、そういう整備をしたという話は聞いております。なかなかやはりこの18の市立小・中学校があって、グラウンドがどうかというのを教育委員会が定期的に見に行ってというところは、少し難しいところがあるのです。
学校にお任せしてしまっているわけではないのですが、何かあったときにはいつでも教育委員会、具体的には教育企画課の財務係というところになりますが、そこに風通しよくお話しいただける、ちょっと困ったこんなことがあるのだけどと、そういうお互いの関係をつくっておくということはすごく大事だと思っています。物理的に、もういつでも見に行ってということができれば、本当は一番いいのでしょうけれども、やはりそこは人的リソースとしては限界がありますので、いつでも御相談くださいというふうにしているのが基本スタンスというところはあろうかと思っております。
先ほども申し上げたとおり、そうはいってもやはり定期的にどこかでは見たいというところがありますので、少し答弁の中でも言いましたが、専門業者を入れて、9校ずつ隔年になります。隔年で専門の業者のチェックを入れて、だからそういう意味では、2年に1回はそういった視点が入るという形にはなっております。 -
13:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。確かに先ほど専門の業者さんの話が出ましたので、そこは期待するところではあります。
すみません、これも提案の仕方、やり方の問題なのですけど、教育委員会さんにもっと頻繁に行ってくださいと言っているつもりもなく、そうではなく、学校側から報告することのハードルを下げたらどうかなと思うのです。要するにアンテナを高くするということです。自分の教育委員会側のアンテナを高くするためには、ハードルを下げればアンテナが高くなると思うのです。そうすると学校側もいろいろなことが、あっ、こんなことまで教育委員会に言っていいのだな、言ったほうがいいのだなということになってくると思うので、そこをちょっと工夫しながら。ここで言っていた、どういうルールを今後つくっていくのですかという質問はそういうことで、もう少しやり取りをうまくしながらやってほしいなと。
グラウンド整備に関する計画的な整備というのは、ある程度の計画性を持ってやっていく。だけどそれは工事だけではなくて、様々なことを連絡を取りながら、来た情報に対してはきちんと反応していくということを、頻繁にもう少しやっていただきながらやるのだよという、何かそういう方向性を打ち出していただいて、私、すみません、グラウンドの話にばかりになってしまっていますけど、もう少しグラウンドをかわいがってほしいです。グラウンドをかわいがることで、生徒たちには本当にいい環境を提供することができると思うので、今後ぜひ検討していただきたいと思いますので、最後に御見解をお願いいたします。 -
14:
◯教育部長(真柳雄飛君) 先ほど私が申し上げた風通しのいいというところは、言い換えれば教育委員会側のハードルを下げるというところにつながっていくのだろうとは思っておりますが、今もいろいろなお話は確かに、教育企画課のほうに来ております。それはグラウンドに限らずです。
特に予算の時期になれば、どういったことがあるかという要望を聞いて、こちらのほうでもある程度限られた予算ということになりますので、優劣をつけてというところにはなりますが、そういう定期的な予算の時期というところもありますし、日常的にも何かあれば御相談いただいていると思っておりますけれども、確かにもっとコミュニケーションを取ってというところはできる方法というのはあると思いますので、そこはまた考えてみたいというふうに思います。