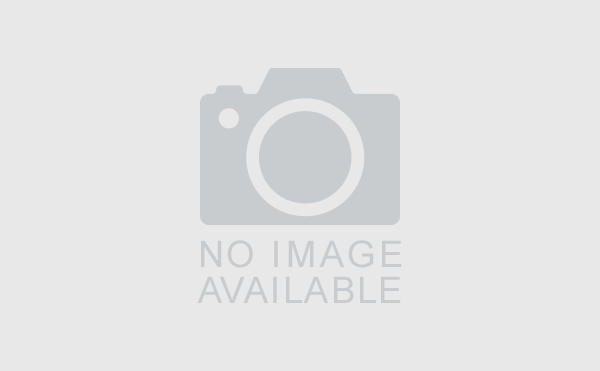令和6年第2回定例会 2024-06-14(録画中継と議事録抜粋)
-
令和6年第2回定例会 6月14日(金) 本会議 一般質問
- 教育現場における合意形成、安全・安心のまちづくり、適正な契約について
・教育現場における情報共有、合意形成について
・学校施設の利活用に関する情報共有、合意形成について
・安全・安心のまちづくりについて
・随意契約について

- 議事録
◯6 番(宮代一利君) 6番、ワクワクはたらく、宮代一利でございます。よろしくお願いします。
現在、武蔵野市議会始まって初めての子ども議会を開催するということで取り組んでおります。8月18日が本番で、本会議場のこの壇上で学校ごとに発表する流れになっています。6月1日に最初の準備会議を開催しました。今後は7月17日に詳細の検討会を開催する予定です。今回は中学生を対象として、全6校から、2年生と3年生合わせて15名が参加してくれることになっています。
先日の準備会は参加生徒も初顔合わせだったので、最初は遠慮がちでしたが、だんだんと意見も活発に出てきて、笑い声に満たされ、盛り上がってきました。そうなりますといろいろな本音も飛び出して、大人が気づいていない感性に触れることもできました。幾つかはっとさせられる意見がありましたので、御紹介させていただきます。
学校のロッカーに扉を設けて、できれば鍵もつけてほしい。教室が狭い。机の横の間隔が狭い。荷物を足元に置くので、教室内を移動するときに荷物をまたがなければならない。かばんが重い。定期テスト前には、毎日教科書を全部持ち帰る必要がある。タブレットも重い。仮設校舎で雨漏りがひどい。網戸が古くて危ない。
給食が多い。全ての学年が余っている。このことは、そこにいたテーブルの別の学校では逆に、少ないという意見も出ていて、いろいろ学校によって事情が異なるようでした。それから給食について、カレーにレーズンきもい。すみません、当日の発言のままで御容赦ください。キャベツにショウガ、要らないと思う。ドレッシングを自分でかけるスタイルを希望する。卒業記念に卒業生がお気に入りのメニューを話し合う企画があるが、その結果を反映した給食が出てくるのは次の年度になってからである。かわいそう。
塾帰りに駅前に大人がたまっていて怖い。夜道が暗い。
このようにいろいろな意見が出てきました。カレーのレーズンとかキャベツのショウガとかは、私は普通ではないかと感じましたけれども、食文化は変化しているのだなと実感した次第です。例えば給食のことなど、声を上げて伝えればいいと思うけどと言ったところ、作ってもらっているのにそんなことは言えないという感想が返ってきました。本件については、今回は経緯の報告とさせていただきますが、最終的にまとめた成果を基に、9月議会以降、質問として取り上げていきたいと考えています。
今回の通告にちょっと明記しなかったのですけれども、こういった中学生の意見を市政に反映することについて、ふだんからどう考えているのか、また、どのような方法で意見や気持ちに触れようとしているのか、もし基本的な方針についてコメントがあればいただきたいと考えているところです。
それでは質問に移ります。1番、教育現場における情報共有、合意形成についてです。
質問1の1、教育内容に関する児童生徒との情報共有、合意形成について。今回の一般質問を準備する中で、学習指導要領を読んでみようという気持ちになりました。今さらすみません。今まで読んだことがなかったです。300ページを超える超大作で、先生はこれを頭と心に刻み込んでいるのかと思うと、驚きとともに頭が下がる思いでした。
質問、まず1番です。学習指導要領の効能と縛りについて。先生にとって学習指導要領というのはどんな存在なのかを伺いたいと思います。
2)児童生徒の感想、意見、希望を反映することについて。私の育った昭和の時代は、今さらながら時代が違ったなと改めて感じます。学校において先生は絶対で、ひたすら正しいことが書いてある教科書の内容を先生から教わるという感覚でした。現在の日本における教育も、いまだ一方通行と感じる場面もありますが、そのスタイルを変えていくという考えがあるのか、何が課題なのかについて伺いたいと思います。
3)合意形成をするための手法について。学校教育において、生徒の意見などを聞いて生徒と先生の間で合意形成するためには、まず現在の状況を把握する必要があると考えますが、それを調査することについて何かお考えがあるのか、既に取り組んでいることがあるのか、また、現状を把握した上で、合意形成に向けてディスカッションをすることができると考えているのか、伺いたいと思います。
次です。小学校と中学校の運動会を見に行きました。中学校はコロナ禍の前に戻ったなという印象でした。一方、小学校はコロナ禍で短縮した時間のまま、午前中で終わってしまう学校もありました。運動会終了後は、午後は授業を実施しているという学校もあると聞いています。
そして今年から大きな変化がありました。徒競走で順位をつけないという新しい形に変化していました。4人、5人の複数の児童が走るので、事実上の順位はついているのですが、ゴールした後に1、2、3と書いた旗に並ぶという形をやめる選択をしていました。また、紅組、白組という団体競技をなくし、総合得点で勝ち負けをつけるという形もなくなっていました。
何人かの児童に感想を聞いてみたところ、割とシンプルに受け止めているなという印象でした。児童は過去を知らないので、こういうものだと受け止めているのだなといったところでしょうか。中には、体育が得意で足が速い児童は、残念だ、せっかく活躍できる場面なのに、自分にはここしかないという感想もありました。保護者の反応も様々で、特に午前中で終了するということについては、肯定的な意見もありました。最も敏感に反応していたのは卒業生。現在高校生、大学生、社会人になっている先輩たちとその御家族が、とても残念だというような感想を述べていました。中には、あり得ない、そんなのおかしい、子どもたちがかわいそうと、これまたストレートにおかしいと感じている様子でした。
人間は様々な事象に向き合うとき、自分の経験を基に反応し、判断するのだなと、改めて感じました。私も最初に話を聞いたときは、何だか変だなと思ったのですが、会派内で話をしていくうちに、私の感覚は古いのだ、昭和の感覚なのだということに気づきました。また受け止め方の違いは年代によるものもありますが、それだけでなく、個人の個性による違いもあるのだと感じています。
今回の運動会の路線変更に関し、武蔵野市立第一小学校PTAの第5回運営委員会──2024年1月29日開催──の席で、校長先生から、運動会や学芸会などの学校行事についてです。運動会や学芸会は音楽会や展覧会と違って、何かの教科に立っていない独自のものなので、教育内容にフィットしていません。保護者の方にとっていろいろな思い出のある行事だと思いますが、学芸会などは経験していない教員が増えている状況なので、そろそろ見直しの時期になっていると感じています。学校教育活動を、来年度ではなくても、何年か単位で見直しをしていかなければならないということを皆さんに御理解いただけたらと思うので、よろしくお願いしますとの発言があったとの記録が、ホームページ上に残っています。
この何かの教科に立っていない独自のものなのでとの表現が何を意味しているのか、いまだに私は理解できていません。ここを理解しようと考えて、学習指導要領をひもといてみたわけです。徒競走の順位を明らかにしない。団体での勝敗を決めない。ここが変更の一つのポイントだったかなというふうに感じています。
しかし学習指導要領の第9節、体育、第2、各学年の目標及び内容、1、2年生のところで、A、B、C、D、EのE、ゲームという箇所があって、そこに「(3)運動遊びに進んで取り組み、規則を守り誰とでも仲よく運動をしたり、勝敗を受け入れたり、場や用具の安全に気を付けたりすること」と明記されているのです。学年ごとに表現の異なる箇所もありますけれども、この表記は低学年も高学年も同じです。この時点で、順位を明らかにしないことが学習指導要領によって生まれた発想ではないことが分かります。そんなことが起こっている中、今回質問いたします。
質問1の2です。学校行事に関する保護者との情報共有、合意形成について。
1)です。運動会は一例ですけれども、様々な行事の取り組み方の路線を変更する際、保護者にはどんな形で情報共有をしているのでしょうか。保護者との情報共有の方法について伺います。多くの情報を共有しようとすると、そのことが先生の負荷になる可能性もあるかと思います。実際現状はどう感じているのか伺います。さらに現状で情報共有について課題があれば、それを伺います。
2)学校行事に関する学校と保護者との合意形成は可能なのか。前述のとおり、情報共有を進めた上で様々な感想、意見が出てくることと思います。現状でも、直接学校に訴えかけている保護者もいるのかもしれません。まず学校に意見が届くように、何か方策を立てているのかを伺います。また、意見が届いたとして、様々な意見があると想像されますし、前述した運動会の例のように、賛否が分かれるケースも考えられます。学校としてはそういったことに対し、どのように対応していく方針なのか伺います。最終的に合意形成についてのお考えを伺いたいと思います。
大きな2番です。学校施設の利活用に関する情報共有、合意形成についてです。
運動会の運営が大きく変化していることを知り、改めて児童生徒と学校との関係、保護者と学校の関係について考えています。
まず、青少年健全育成に目を向けてみます。令和6年度武蔵野市青少年健全育成運動推進方針には、1の趣旨に、「青少年が「自らも地域の一員であり将来の担い手である」という自覚を持ち、社会性を身に付け、主体的に行動できるように育成していくためには、家庭や地域が学校や行政等の諸機関と共通の方針を持って、相互に緊密な連携を図りながら、青少年の健全育成運動に取り組むことが重要です」と記載があり、2番の重点目標と行動計画の(2)の地域社会による健全な社会環境づくりの推進には、「地域社会は、青少年の人間性を育む場として重要な役割を担っており、次代を担う青少年を育成する場としての機能を強化していく必要があります。1)青少年が地域事業へ参画し、自らも地域の一員としての役割を果たすことなどを通じて、青少年の生きる力を育成していきます。地域社会との関わりが薄い青少年に対しても、地域の大人が挨拶や地域行事への参画等の声掛けを行うことで、青少年と地域との関係の醸成を図っていきます」。中略して3)です。「子どもの育ちの段階ごとに応じた途切れ・隙間のない支援が必要であるとの問題意識を持ち、関係機関と連携した継続的な支援を行っていきます」となっています。
そして、本方針における推進団体として、青少年育成団体・青少年団体などが定義づけられています。
このように、今読んだ中でも、地域とか地域社会という言葉が何度も出てきて、この関係性が重要であるということが書かれていて、家庭や地域が学校や行政などの諸機関と連携する必要があるとの考えに立っていることが分かります。
質問の2の1です。地域に開かれた学校について。
1)開かれた学校づくり協議会の現状と今後について伺います。学校運営協議会機能を有する開かれた学校づくり協議会──ちょっと名前が長くてなかなか飲み込みづらいのですが──という新しい形について、活動が続いていると認識しております。この活動によるこれまでに得られた結果と今後の展開について、詳細の御説明をお願いしたいと思います。
学校と地域の関係性について、運動会における実例があります。運動会に向けて、グラウンドに設置されているサッカーゴールなどの設備は取り外されて移動します。運動会終了後にはこれらを原状復帰する必要があって、原則先生たちが行うものだと思いますが、育成団体を中心に保護者が復旧を手伝っている学校が複数あると聞いています。まさに地域と学校が連携をしている一つの例であると感じます。これはルールというよりも、自主的な活動であり、良好な関係性の結果起こっている事象であると考えます。育成団体は長い歴史の中で、その関係性を築いてきています。今後もこれらを発展させ、よりよい活動につなげていきたいと考えています。
質問の2)です。学校と地域の関係性について、現状と今後について伺います。
大きな質問2の2です。学校施設利用について。学校施設の団体利用について、施設開放委員会が組織されています。そのトップは副校長先生です。この委員会においては、利用団体間のスケジュール調整などが主な目的と考えられます。今回は団体利用に関する考え方、現状、今後の方向性について整理したいと思います。
学校施設は誰のものか。市税でつくったものですから、市民のものなのではないかなと考えています。日常の運営について、校長先生、副校長先生に権限があると思っていますが、この権限とは何なのか。明確に議論したことはなく、様々な場面で、学校から言われることは素直に受け入れるという感じになっているとの印象です。学校教育と団体利用の関係を考えれば当然のことですが、学校教育での利用が最優先であることは自明の理です。では、その他の学校施設の活用についてはどんな考え方をしているのか、もう少し情報を提供いただけると助かります。
また運動会の事例を示しますが、運動会が近づくと、練習のためにグラウンドにラインを引いて準備にかかります。そのほかサッカーゴールなど、グラウンドに設置されている備品類を移動することは先ほども申し上げました。今回に限ったことではないと思うのですが、私が新たに知ったのは、学校によって運動会前のグラウンド貸出し許可期間が異なるということです。1か月ほど前には完全に貸出しをやめてしまう学校もあれば、ゴールなどはないものの、ぎりぎりまで貸出しをしている学校があるということです。この違いは何に起因しているのか。長期にわたり閉鎖になった学校の育成団体から悲鳴の声が上がりました。1か月にもわたって団体活動を休止することは、その団体にとって、子どもたちにとって、大変苦しい状況です。これを踏まえて、以下質問します。
1)施設利用に関し、本来の教育活動と地域活動とのバランスについての考え方について伺います。
2)育成団体への情報共有の方法、要望に対する対応の方法について伺いたいと思います。
大きな3番です。安全・安心のまちづくりについて。
今年度の代表質問において小美濃市長より、「市民が自らのまちを守るという意識、これは大変大事であります。いわゆる地域愛ということが、まちをよくしていく大きな原因だと思っております。しかし、地域だけではなかなか解決できない諸問題、諸課題、これはあるかもしれません。そういった場合には、行政の支援が必要になってくることもあり得るかもしれません。全てに対して支援ができるということはここで申し上げられませんけれども、そういったことに関しましては、地域の皆さんと、また行政としっかりと協議をし、安全・安心なまちづくりに努めていきたい、このように考えている次第であります」との力強いお答えをいただいているところです。今回はこの方向性を前提として、具体的な動きについて伺いたいと思います。
質問3の1、ブルーキャップについてです。
1)ブルーキャップについてはしっかり取り組んでいただいていると感じている一方で、効果を測ることが難しいと感じています。まず、これまでの取組について、予算規模、委託状況、人数であるとか、活動時間であるとか、活動範囲であるとかなど、それから活動実績の推移について伺いたいと思います。
2)目指す方向性、目標について伺います。これまでブルーキャップについては何度か一般質問してきたのですが、なかなかこの議論がかみ合わなくて、方向性を示していただくことができなかったというふうに考えております。市長が替わられましたので、新市長から、このブルーキャップの目指す方向性、どこを目標にしているのかということについての御見解を、ぜひ伺いたいと思います。
それから、3)委託事業の発注仕様、検収方法について伺います。これは非常に実務的な話です。ブルーキャップは通常に委託事業としてやっているわけで、まず発注するためには発注の仕様書が存在しているはずで、また、その仕様に基づいて検収してお金を支払う際には、何か成果があって、その成果の報告が生じて、それを検収することによって初めて支払いができる、そういう仕組みになっているはずで、ここがちょっと今までのやり取りにおいては、何で検収をして、どうやってお金を支払っているのかということがよく分からないまま、今に至っているというふうに私は感じています。ぜひ委託事業の発注の仕様と、その検収の方法について伺いたいと思います。
それから質問の3の2です。これはブルーキャップだけではないのですけれども、路上喫煙について。
1)路上喫煙の現状と課題について伺いたいと思います。
2)トレーラーハウスの現状と評価について伺います。
3)路上喫煙・ポイ捨て撲滅に向けた今後の取組について伺います。
特に目立つのは、やはり夜のまちで客引きをやっている、要するにブルーキャップの取締り対象となり得る方たちが、たばこを吸いながら客引きをしているという、これが非常に目立つ状況があると思います。こういったことをはじめとして、路上喫煙について今後どういうふうにして撲滅をしていこうと考えているのか、ぜひ伺いたいと思います。
分析できていないのですけれども、私はたまたま毎週のように川崎市の新百合ヶ丘に足を運ぶことがあって、駅前をずっと歩くのですけど、約15分ぐらい駅から住宅街も歩くのですが、もう半年以上行っているのですけど、一人も路上喫煙を見たことがないのです。何でなのだろうと。よく分かりません。1つ、課金、過料です、罰金を取っているというその表示があって、ここで吸ったら3,000円ですよというようなことが書いてあって、それなのかなと思うのですが、とにかくいまだ一人も見たことがないというすごい状況なので、ちょっと私はこれはぜひ研究をして、どうしたら武蔵野市で路上の喫煙というのを完全に撲滅することができるのかということについて考えていきたいというふうに思っております。
さて、4番の随意契約について。またかというふうに感じていらっしゃる職員の方もいらっしゃるのかもしれませんが、また取り上げなければならないという状況なのです。この原稿を私が準備しているさなかに、これは随意契約ではないですけれども、固定資産税、都市計画税の課税誤りについて(報告)という紙が私のところに来ました。皆さんのところにも来ていると思います。これは総務委員会で行政報告を行いますと書いてあるので、そこで詳細を伺うことになると思いますが、3番に再発防止策と書いてあります。今後は課税業務の事務処理手順を書面化した上で、担当職員間での情報共有を図るとともに、チェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいります。
この文章はもう何度見たでしょう。どこもかしこも監査をする。監査に注意される。必ず判で押したようにこのことが書いてあります。これは直らないですよね。チェック体制を徹底し、再発防止に努めてまいりますと、こう一文書いて、これで監査の報告書にも毎回このことが書かれている。一向に直らない。これは私は、ブルーキャップのほうでは、もう完全に路上における客引きをゼロにするのはなかなか難しいのだろうなというところは分かるのですけど、この随意契約に限らず、監査における指摘事項というのは、やはりヒューマンエラーを含めて、ゼロを目指すべきだというふうに私は考えています。そういう前提において質問をいたします。
4の1、随意契約に関する定期監査での指摘について。定期監査における随意契約に係る指摘の推移と、そのことに関する評価、認識について伺いたいと思います。
質問4の2、指摘を受けての改善策について。指摘に対してどのような改善策を今まで実行してきたのか、また今後はどういうふうに取り組んでいこうとしているのか、再度市長の御見解を伺いたいと思います。
それから、質問4の3です。システムの改修の現状について。令和5年度の一般質問の回答の中で、システム改修しますと。どういうことかというと、一番多いのは、なぜ随意契約にしたのですかという理由を必ず書かなければいけないとなっているのですが、その記載漏れということがもう度々繰り返されていて、そのためには、システムに打ち込むと、そこに記載がないとアラートが出て、これでは未完成ですよというふうにするというイメージで、私はシステムの改修ということを捉えていたのですが、ヒューマンエラーを減らすためにシステム改修するという方策について、この進捗状況、今どこまで進んでいて、それが効果が出ているのかなど、この進捗状況について伺いたいと思います。
以上、壇上からの質問といたします。どうぞ御答弁のほど、よろしくお願いいたします。 -
35:
◯議 長(落合勝利君) 暫時休憩をいたします。
○午後 0時11分 休 憩
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○午後 1時40分 再 開 -
36:
◯議 長(落合勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
-
37:
◯市 長(小美濃安弘君) それでは、宮代一利議員の一般質問にお答えをいたします。
まず、私からは大きな3点目の安全・安心のまちづくりについてお答えいたします。
大きな3点目の3の1の1、ブルーキャップの予算規模、委託状況、活動実績についての御質問であります。令和6年度委託事業の予算は6,601万4,000円であります。
令和6年度の委託状況でありますが、業務委託をしている目的は、公共の場所における必要な付きまとい勧誘行為や客引き行為などの指導、路上宣伝行為などの適正化を図ることにより、市民や来街者が安全・安心に通行できる生活環境を確保するということであります。人数は、月曜日から土曜日が9人体制、日曜日、祝日が7人体制となっております。活動時間は、月曜日から土曜日が13時から24時まで、日曜日、祝日が13時から22時30分までとなっております。活動範囲は吉祥寺駅周辺です。
活動実績についてですが、禁止行為の口頭注意が、令和4年度2,214件、令和5年度5,457件、禁止行為の指導が、令和4年度5件、令和5年度ゼロ件、禁止行為の警告が、令和4年度4件、令和5年度3件、路上宣伝行為の方法の変更要請が、令和4年度278件、令和5年度324件となっております。
次に、3の1の2、ブルーキャップについて、目指す方向、目標についての御質問であります。風俗店などによる客引き、客待ちなどの実態に即した形で、ブルーキャップや吉祥寺ミッドナイトパトロール隊の活動方法を、より効果があるよう見直しをするなど、禁止行為が行いづらい環境づくりを目指していきたいと考えております。
次に、3の1の3)委託事業の発注仕様についての御質問であります。仕様書の項目は、件名、目的、履行期間、委託内容、事故等の対応、損害賠償責任、一般的注意事項、支払方法、その他事項となっております。選定方法は、選定の審査基準は指名型企画提案方式によるプロポーザルにて委託事業者の選定を実施し、技術点と価格点の総合評価により、優先交渉権者を決定いたしました。
なお、技術点の主な評価項目は、業務に対する理解度、類似する業務の実績、吉祥寺駅周辺地域の現状分析や、客引き行為などを行う者への対応方法、従業者の体制などであります。
次に、委託事業実施の確認についての御質問であります。仕様書に基づき、1日の業務終了後の翌日、市役所が閉庁時の場合は翌開庁日までに、市が指定する報告書により、パトロールの実施状況の報告が市に対して行われております。また月初めには、前月分の月報の提出を受けております。安全対策課におきまして、その報告書により日々の業務内容を確認し、つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例に基づく指導業務が適正に行われているか、確認をしております。
また現状や課題等につきましては、委託事業者、安全対策課により、3か月に一度検討会議を実施し、情報共有を行うとともに、課題解決に向けた検討を行い、必要な見直しを行い、事業実施の実効性を高めているところでございます。
次に、路上禁煙についてであります。路上禁煙の1、路上禁煙の現状と課題についての御質問であります。失礼、路上喫煙です。路上喫煙の現状と課題についてであります。1の路上喫煙の現状と課題について御質問いただきました。市では、喫煙はルールとマナーを守り、吸う人も吸わない人も気持ちよく過ごせるまちづくりを目指して、これまで喫煙対策を行ってまいりました。
これを受けて、各駅前周辺を路上禁煙地区と指定する一方、喫煙トレーラーハウスを設置し、喫煙できる環境を整備しております。これまでの啓発、マナー指導等により、路上禁煙地区においては、日中は喫煙者は目立ちませんが、夜間は吉祥寺地域において喫煙者が多く、たばこのポイ捨ても多く見られているところであります。喫煙者と非喫煙者とがうまく共存していける喫煙対策が課題と認識をしております。
次に、2)のトレーラーハウスの現状と評価についての御質問であります。コロナ禍により利用人数を6人に制限しておりましたが、令和5年1月から制限を撤廃し、吉祥寺、三鷹については12人、武蔵境については10人まで利用できるようになりました。また、同年4月から利用終了時間を2時間延長し、吉祥寺につきましては23時まで、三鷹、武蔵境については21時までとしております。
利用時間を通して多くの方に利用していただいております。また時間帯によっては、空くのを待って並んでいる様子も見受けられますが、おおむねマナーよく使っていただいていると認識をしております。喫煙トレーラーハウスの設置前後で、喫煙マナーの指導件数、吸い殻の本数が大きく減少したといった結果は見受けられませんが、喫煙トレーラーハウスが次第に認知されてきて、多くの方に利用していただけておりますので、受動喫煙の防止には大きな効果があったと評価をしているところでございます。
次に、3)の路上喫煙・ポイ捨て撲滅に向けた今後の取組についての御質問であります。引き続き、路上禁煙地区の周知、喫煙のマナーアップに向けた啓発、ブルーキャップと連携した指導を粘り強く行っていくほか、喫煙の状況を伺いつつ、市民団体、商店会など、まちの関係者と連携して、喫煙トレーラーハウスの設置、路上禁煙地区の拡張の検討をしてまいります。
次に、随意契約についての質問でございます。随意契約に関する定期監査での御指摘についてでございますが、現在、令和5年度第2回定期監査を実施中のため、令和5年度第1回分から令和元年度分についてお答えをいたします。随意契約に係る令和5年度の指摘件数は7件で、内容は、随意契約とした根拠法令や号数や契約した業者を指定した具体的な理由の記載が漏れていたものが2件のほか、個人情報特記仕様書の添付が漏れているものや、改正前の個人情報特記仕様書が添付されているものが3件、仕様書や再委託確認書、再委託承諾書の添付が漏れているものが2件でございました。
令和4年度の指摘件数は13件で、内容は、随意契約とした根拠法令の号数や、契約した業者を指定した具体的な理由の記載が漏れていたものが7件のほか、収入印紙の貼付漏れ、予定価格、比較価格の記載漏れ及び私印決裁されていたものが6件でございました。
令和3年度の指摘件数は7件で、内容は、見積り合わせを2者以上でしなければならないところ、1者でしか行っていなかったものが1件のほか、随意契約とした根拠法令の号数や、契約した業者を指定した具体的な理由の記載漏れが6件でございました。
令和2年度の指摘件数は13件で、内容は、分割発注に見えるものが1件、見積り合わせの業者数が不足するものが4件のほか、指定理由の記載漏れ、随意契約とした根拠法令の記載誤りや記載漏れ、契約した業者を指定した具体的な理由の記載漏れが8件でございました。
令和元年度の指摘件数は9件で、内容は、分割発注に見えるものが2件のほか、指定理由の記載誤りや記載漏れが7件でした。
監査指摘事項は、例年同じような誤りなどがあることについて残念に思っております。これまでも行ってまいりましたが、職層別の契約事務研修等の受講を含め、契約事務の理解を繰り返し促すとともに、改めて課内のチェック体制の強化、法令、要綱、マニュアル等を確認し、適正な事務処理を行うことを徹底していくなど、不断の努力を続けていく必要があると考えております。
続きまして、指摘を受けての改善についての御質問であります。これまでも実施しておりますが、庁内における研修として、新任職員向け研修、担当者向け契約事務研修、課長補佐、係長及び新任管理職に向けたリスクマネジメント研修を別個に行い、それぞれの職層に応じた4つの研修をきめ細かく展開しております。職層別の契約事務研修等の受講を含め、契約事務の理解を繰り返し促すとともに、改めて課内のチェック体制の強化、法令、要綱、マニュアル等を確認し、適正な事務処理を行うことを徹底していくなど、不断の努力を続けていく必要があると考えております。
次に、システム改修の現状についての御質問でございます。昨年度の一般質問でお答えしたとおり、令和5年度に、指定理由の入力漏れについて、入力がなく処理を進める場合に、エラーの注意喚起を表示するシステムの改修を行いました。令和5年度の指摘事項は、手入力による自由記載の欄に関してのため、システムでは対応できない案件について指摘を受けましたが、以前に課題となっていた指定理由の入力漏れについては改修を行い、発生しておりません。
令和5年度の監査が実施中のため、件数の比較は難しいところでございますが、引き続きヒューマンエラーを減らすよう、システムももちろんでございますけれども、職員の契約事務への理解を深め、全庁で努力をしてまいります。
私からは以上でございます。
残る質問は、教育長職務代理者よりお答えをいたします。 -
38:
◯教育長職務代理者(清水健一君) まずは、8月18日の子ども議会のお話、ありがとうございました。子どもたちがしっかりと話を聞いて、建設的な話合いができることを期待しております。よろしくお願いします。
それでは、宮代議員の御質問にお答えします。
まず、1の教育現場における情報共有、合意形成について。1)教員にとって学習指導要領はどんな存在ですかということですが、学習指導要領は、全国のどこの地域で教育を受けても一定の水準の教育が受けられるようにするために、文部科学省が定めたものであり、各学校が教育課程を編成する際の基準となるものです。先ほど三百何十ページというお話がありましたけど、今持ってまいりました。これは総則。これが学習指導要領です。こちらの総則については記述の意味とか解釈が細かく出ていて、学習指導要領は各教科の目標とか内容が出ております。あとこのほかにも、各教科の細かい教科ごとのものがあります。この緑色のが小学校で、この黄色いのが中学校です。
続きまして、2)日本における現在の教育についてですが、現行の学習指導要領は、主体的、対話的で深い学びの充実が、授業改善の大きなポイントとして示されております。学校は授業をはじめ、様々な教育活動の工夫、改善に努める必要があります。そのため市内各校では、教員と児童生徒相互だけでなく、児童生徒とのやり取りを大切にする授業展開に変わってきています。課題としてよく言われるものとして、今の教員自身が子どもの頃にこのような授業を受けておらず、イメージを持ちづらいというものがあります。そのため教員研修等では、対話や合意形成を体験するようなプログラムを取り入れております。
3番目の御質問ですが、児童生徒の現在の状況については、毎年行われる全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙に、あなたの学級では、学級生活をよりよくするために学級会──中学校は学級活動ですが──で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決めていますかという質問があります。この推移に注目してます。令和5年度の現状としましては、小学校では都や全国の平均を上回っているものの、中学校に関しては下回っております。この状況を踏まえ、児童生徒が日々の教育活動に対しても、学校評価などを通して意見を述べる取組を推進しています。指導課が資料を作成し、各校でも様々な場面で児童生徒が多様な意見を出し合い、認め、生かす授業改善に取り組み、少しずつ変わってきているところであります。
次に、質問1の2、学校行事に関する保護者との情報共有の方法についてお答えします。まず、どのように情報提供されているかということですけれども、学校だより、保護者連絡帳、学校ホームページ、それから保護者会を活用して情報を提供しています。
次に教員の負担についてですが、情報提供することは社会に開かれた教育課程に必要な業務ではありますが、教員の負担にならない工夫が必要であると考えています。
最後に、情報提供に関する課題についてですが、時期を逸しないタイムリー性、相手に伝わる明確なメッセージ性、相手に着実に届くかの確実性が課題となると考えています。
2番目の御質問ですが、学校行事の際に保護者の様々な考えを聞いているかですが、行事実施のたびに保護者へアンケートを実施し、御意見を聞いております。合意形成を図ることができるかという観点からは、学校には様々な意見が寄せられるため、全てを受け止めることは難しい部分もあります。学校は意見を受け止めた上で、行事の目的等と照らして改善に生かしています。
続いて、御質問の2、学校施設の利活用に関する情報共有、合意形成についてお答えします。
まず、1)開かれた学校づくり協議会の現状と今後についてですが、本協議会の機能強化を図るため、昨年度から学校運営協議会の機能を有する開かれた学校づくり協議会のモデル校を2校設定し、研究を進めており、令和7年度より市内全校で全面実施していきます。この全面実施に向けて、市内各校で開かれた学校づくり協議会の委員の多様性を実現できるようにするとともに、協議会での継続的な熟議が展開できるよう、通信を通じて取組紹介や研修を引き続き行ってまいります。
2番目の御質問についてですが、学校と地域の関係性について、令和3年度より2年間をかけ、学校・家庭・地域の協働体制検討委員会で協議してまいりました。その中で、学校と地域の互いの状況を理解し合い、強みをコーディネートしていくことなどが課題として確認されました。さきの開かれた学校づくり協議会の機能強化を含め、学校、地域が協力していくことが一層重要になります。
2の2の1)です。学校施設利用の教育活動と地域活動のバランスについての御質問ですが、地域活動の学校施設利用につきましては、武蔵野市立学校施設の開放に関する条例により、利用できる施設や料金、学校教育に使用する時間を除いて、市民に使用させることができる旨を規定しています。学校教育に使用する具体的な事例としては、運動会や部活動などの準備行為を含む使用期間が挙げられますが、この期間は地域活動の使用に開放していません。地域の皆様にこうした期間についての御理解を賜りつつ、皆様の御意見や御要望も伺い、学校施設を学校教育活動、地域活動に気持ちよく利用できるよう、調整を図っていきます。
続いて、2)の育成団体からの要望の取扱いについての御質問ですが、市内の小学校と第二中学校、第四中学校、第六中学校につきましては、各校副校長を管理者とする学校施設開放委員会で団体の要望を調整し、委員会のない第一中学校、第三中学校、第五中学校につきましては、副校長と各団体で調整をしていただいています。委員会で検討された事項については生涯学習スポーツ課にも伝達がされます。委員会だけでは対応が難しい案件については、必要に応じて生涯学習スポーツ課においても対応を検討することがあります。
以上です。 -
39:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございました。まず、市長にお答えいただきました安全・安心のまちづくりですけど、一番最初にブルーキャップが始まってから、去年ですか、予算を少し大きくして、人数、時間も変更したというふうに認識をしていて、その変化をさせたことによって、どれぐらい効果が出たと見ているのか、そこをぜひ伺いたいです。
この先のことを知りたいというのは、要するにまだそもそも完成していないですよね、きっとこのブルーキャップの活動というのは。もう100%これでうまくいったとなかなか言い切れないと思うのですけど、どこまで追い込んでいくつもりなのか、どうやってこれから対応していくつもりなのか、もう少し掘り下げていただきたい。
今これではまずは、申し訳ないのですけど、あえて今回発注仕様書、それから検収方法と申し上げたけれども、要するに、やっていることに対する、これがどう評価されているのかということをもう少し明確にしていかないと、せっかくやっているのに、そのことが市民の中でなかなか評価されていないなということを感じていて、将来にわたる動きについてもう少し語っていただきたいなというふうに思っています。
それから、路上の喫煙の話ですけど、先ほど市長の御説明の中に、今後設置、それから拡張という御説明が最後にあったのですが、この設置とは、何をどれぐらい設置するということを意味していたのか、それから拡張というのは、何を拡張するということをおっしゃったのか、もうちょっと具体的に教えていただきたいと思います。拡張、設置については非常に期待するところがありまして、ぜひここで教えていただきたいなというふうに思っています。
それから契約の件ですけど、数字を見ると7、13、7、13、9というふうにして、ほぼ横ばいと見えていて、相変わらず何も変わっていないと。非常に、えっと思ったのは、令和5年にシステム改修を行って、先ほどの御説明のとおり、選択をする部分についてはエラーはなくなりましたけれども、やはり手入力のところにエラーが残ってしまっているという御説明をいただいたのですが、今後この部分をどうされるつもりなのか。
要するに、何かほぼシステム改修するとか、激減するぞということをちょっと期待していたのですけど、部分的にしか改善されていないということが今回の検証で分かってきているので、さらにそのどこを掘り下げていって、どういうふうにゼロを目指すのかということ。私はあえて壇上でゼロという話をしましたけれども、市長もゼロを目指しているというふうにおっしゃっていただけるのかどうか、そこが非常に私は重点だと思っています。
以上、お願いします。 -
40:
◯市 長(小美濃安弘君) まず、ブルーキャップをどのように評価しているかということであります。先日、私はブルーキャップの方と吉祥寺駅周辺の防犯カメラの設置状況について、一緒にパトロールをさせていただきました。パトロールをしている最中も、客引きと見られる人たちに対してしっかりと指導を行っておりましたし、路上喫煙をしている人にも、これは喫煙のマナーアップの指導員もいるのですが、ブルーキャップの人たちも併せて、ここは禁煙地域だからたばこは御遠慮くださいということで、しっかりと指導している姿を見させていただきました。
最終的には、先ほどお話をいたしました、公共の場所における執拗な付きまとい行為や客引き行為等の指導、また路上宣伝行為等の適正化を図ることにより、ここが大事なのですが、市民や来街者が安全・安心に通行できる生活環境を確保するということが最終目的でございますので、やはり安全を確保するというのは、今ある安全よりも、さらにまた来年は向上し、またさらに向上しという、これは完成がないと思っておりますので、常に注意を払いながら、特に吉祥寺駅周辺の安全確保に努めていきたいというのが目標でございます。
2点目の何を拡張するのかということでございますが、これは先日、勧誘行為等適正化特定地区の拡張をさせていただきました。それに合わせて、吉祥寺イーストエリアの喫煙トレーラーハウスの設置を今考えております。それに合わせて、先ほどの勧誘行為等適正化特定地区の拡張などもいたしましたので、そこと合わせるのかどうかというのはこれからの議論になりますけれども、こちらのほうを拡張いたしましたので、喫煙トレーラーハウスの設置をするとともに、路上禁煙地区の拡張について検討していきたいということを考えているところであります。
システム改修についての手入力については、まだ一部問題があるようでございますが、これは当然ゼロを目指して頑張っていかなくてはならないと思っておりますし、それに向けて、今後も研修などもしっかりと行っていかなくてはならないと考えているところでございます。 -
41:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございました。まずそのトレーラーハウス新規設置、もう一つ増やしていただけるというふうに受け止めましたので、ぜひよろしくお願いします。効果は出ているのではないかなと、私はトレーラーハウスのやり方はよかったなというふうに思っています。
それから、手入力のところもやはりゼロを目指すというふうに市長はおっしゃっていただいたので、これは本当に頑張ってほしいところです。せっかく複数の方でチェックをしながらやっていて、一番最初に入力をした人がミスしていても、その後順番に判こをついていっている人がいるのですから、絶対どこかで気づいてほしい。
それがチェックできていないのではないかなという思いがあって、この前の教科書のとき、最後、会計課さんがやっとつかまえてくれた。そういう意味では、よくチェック機能が働いたと思いますけど、もっと前にいっぱいの人の目の前を通り過ぎたはずなのに、それが捉えられなかった、最後まで行ってしまったというところ。あれをもうぜひ心に焼き付けてもらって、本当にみんなでなくしていこうという姿勢でやっていただきたいなということを、強く願うところでございます。これは引き続きお願いしたいと思います。
それからブルーキャップです。ブルーキャップについてはおっしゃっているとおりで、これも終着点はないのだけれども、ずっとやり続けることによって、だんだんまちの様子が変わっていっていると思うので、そういったことをきちんと検証していただきたいなというふうに思っています。
最初のところで、検収の方法として、報告書があって、月報があって、それから検討確認会というのがあるというお話だったのですけれども、それは役所の方、防災安全部の方とブルーキャップさんとがミーティングをして、新しいことを考えながら次に進んでいくということを意味していたのかどうか。それはどんなことが話し合われて、どれぐらいの改善点が出てきているのかということを、分かる範囲で結構なので、教えていただきたいと思います。お願いします。 -
42:
◯市 長(小美濃安弘君) ただいまの質問に関しましては、大変細かいことで、具体的なことでございますので、担当よりお答えさせていただきます。
-
43:
◯防災安全部長(稲葉秀満君) 3か月に1回の連絡会のことについて御質問いただきました。今、宮代議員がおっしゃったように、防災安全部と安全対策課、ブルーキャップの事業者等で打合せをしております。やはり現状の直近の傾向とか、立て看板の位置が変わってきているとか、指導の内容について現場での状況を聞きながら、安全対策課のほうでもサポートできる体制について検討し、次回に向けて協議をしているというところでございます。
以上です。 -
44:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。こう言ったら失礼ですけど、月報とか日報とかというのは、大体同じことがずっと続いてくるようになってしまいますよね。だんだんと慣れてくると、前と同じことを書いておけば、これでいいやというふうになりがちなので、そうならないように、やはりその一日一日のそういったところも、ぜひ管理もきちんとやっていただき、かつ、たまにでいいのですけど、一緒に現場にぜひ出ていただきたいなと思います。実態がどうなっているかということは、やはり目で自分で見て、肌で感じていくものだと思うので、ぜひよろしくお願いしたいと思いますので、これからもいいまちづくりをお願いいたします。
さて、教育のほうですけれども、正直申し上げて、今回の運動会の話をさっき少し例を出しましたけど、保護者にはきちんと伝わっていないなという印象です。ちょっとここに一例を示しましたけれども、ある意味唐突に校長先生が行事の見直しをすると。よろしくお願いしますと来てしまっているから、受け止める保護者としては、えっ、何それというふうになってしまっていると思うのです。
そういう情報の伝達の仕方について、やはりちょっとまだ今のところ、あまりよくないぞという御認識はあるのかどうかということを確認したいのと、もしそうであれば、今後どういうふうに変えていくのか。努力しますとか、私はそうではなくて、もっと具体的に、こうすることによって保護者との間にコミュニケーションを取っていくのですというようなことを、もう少し御意見というか、お考えを伺いたいところです。よろしくお願いします。 -
45:
◯教育長職務代理者(清水健一君) 今、宮代議員がおっしゃったことですけれども、すごく大切なことだと思います。
学校と保護者ということで言うと、いろいろと話し合う機会として、保護者会であるとか、年の初めに校長が、今年はこういう学校を進めていきますよという説明があると思うのです。そこで、とにかく丁寧に説明することがまず第一と、それから一方通行ではなくて、説明したことの中で大きく変わることについては、やはりその理由をきちんと述べていくこと、そしてそのことについて保護者が感じた質問を受けることによって、そこでやはり合意形成をしていかないと、不信感を持って、その学校でこれから保護者も子どもも過ごすということがあってはならないと、私は考えております。
そういったことについては、私の立場でできることとしては、いろいろな学校に公開などで行ったときに、今言ったことを話をするというようなことで伝えていくということができるかなと思います。
以上です。 -
46:
◯6 番(宮代一利君) お願いします。今、コミュニケーションということについて御理解いただけて、私は、先生同士も、他校の先生も含めて、もっといろいろな話をしてほしいなというふうに思っていて、ぜひそこも進めていただきたいなと思います。
それからあともう一つ、開かれた学校づくりのところですけど、もっと人数を増やして、オンラインでやりませんか。今すごく限られた人がピックアップされてしまっていて、もうかなり狭い範囲で開かれた学校を考えているのだけど、もうちょっと人数を増やして開かれた学校づくりの協議会というものをやっていくと、いい点を吸い上げることができると思うのですが、そこについて御意見をいただきたいと思います。 -
47:
◯教育長職務代理者(清水健一君) 前の開かれた学校づくり協議会よりも、今度のほうが、倍前後、人数は取りあえず増えています。ただ倍といっても、地域の全体から見ると多くはないので、今宮代議員が言った方法も一つかなと思います。これからそのお考えを受けて、また検討していきたいと思っています。ありがとうございます。
-
48:
◯6 番(宮代一利君) 最後です。生徒との関係において、やはり生徒と双方向的な授業ということで取り組んでおられるという御説明をいただきましたので、これはもうぜひ変わっていく。それで先ほど言ったように、今の教員も、自分が受けてきた教育の残像が残っていると思うので、そこをこれからどうやって変えていくか、もう1回最後にコメントをいただきたいと思います。
-
49:
◯教育長職務代理者(清水健一君) 自分が見てきた授業ではなくて、今もうやられている授業の中で、子どもたちがこれは考えたいなとか、友達と話し合いたいなと、そういう場面をつくる授業ってあるのです。もう出てきているのです。ですからそういうものを先生たちに、もう研究会で見せていく。どういうふうにしたらそれができるのかというノウハウも、実はあるのです。例えば聞き方です。こういう聞き方をすると子どもたちがはっとなって話合いが盛り上がるとか、そういったことが勉強できるように、これから機会を増やしていきたいと思っております。
以上です。