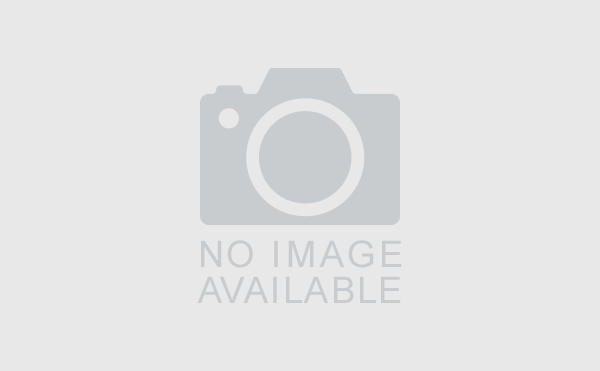令和5年第3回定例会 2023-09-06 本会議 一般質問(録画中継と議事録抜粋)
- 令和5年第3回定例会 9月6日 本会議 一般質問
- インクルーシブ教育、安全・安心のまちづくり、適正な契約について
・インクルーシブ教育について
・安全・安心のまちづくりについて
・適正な契約について - インターネット中継
https://musashino-city.stream.jfit.co.jp/?tpl=play_vod&inquiry_id=2518
議事録
◯6 番(宮代一利君) 6番、ワクワクはたらく、宮代一利です。よろしくお願いいたします。
まず1番目、インクルーシブ教育について。
天畠大輔さんにお目にかかる機会に恵まれました。御存じの方も多いと思いますが、14歳のとき、若年性急性糖尿病により、救急搬送された病院での処置が悪く、心停止を起こし、約3週間の昏睡状態後、後遺症として四肢麻痺、発話障害、視覚障害、嚥下障害など重複障害を抱えています。立命館大学で博士号を取得しております。専門は当事者研究、障害学、社会福祉。現在は参議院議員となっています。病院で寝たきり状態が続き、言葉を発することができず、コミュニケーションの手段を奪われてしまっていました。母親の懸命なアプローチにより、ついに「あ、か、さ、た、な話法」を編み出しました。天畠さんの手記によると、一番最初の頃、ほかに手も動かないし、舌を動かすことによりサインを出すというやり方をしていたというふうに記載がされています。「あ、か、さ、た、な、は、ま、ま、み」、「あ、か、さ、た、な、は、ま、や、や」、「あ、か、さ、さ、し、し」、「あ、か、さ、た、な、は、ま、や、ら、ら、り、る、れ、ろ、ろ」、これで「み、や、し、ろ」という私の名前が出来上がる、これを「あ、か、さ、た、な話法」といっていますが、今は、舌でのサインではなく、恐らく指先が力が入るようになっていて、私どもがお目にかかったときに、サポーターの方がいらっしゃっていて、その方を通して、今のような言葉がどんどんと紡がれていく、そういった「あ、か、さ、た、な話法」というものを編み出しております。今の御説明でお分かりいただいたとおり、時間は大変かかりますが、しかし、しっかりと意思疎通を取ることができました。
天畠さんに会う機会に恵まれ、事前にどんな方なのかということを調べている中で、NHK障害福祉賞というものを知りました。その内容の紹介には、障害のある人御自身の貴重な体験記録や、障害児・障害者の教育や福祉の分野での優れた実践記録などに対して贈るNHK障害福祉賞。半世紀にわたり1万3,000余りの手記が寄せられてきました。長年この賞の選考委員を務めてきた作家、柳田邦男さんは、それを人間理解の宝庫だと言います。人生で直面する壁を文字に書くことによって乗り越えた人々の体験から、私たちは何を酌み取ることができるのでしょうかとあります。受賞作品が公表されており、この夏、たくさんの作品を読みました。それぞれの障害には病名が付されています。しかし、作品を読んで感じるのは、状況も、本人の感じ方も千差万別であること、それぞれの人生を生きているということ、障害者として一くくりにするものではないと改めて強く感じました。
インクルーシブとは、包み込むような、包摂的なという意味です。ソーシャル・インクルージョンとなると、社会的包摂、社会の構成員として包み、支え合うという社会政策の理念から来ています。とても大切な理念で、武蔵野市でもそういった社会の形成を目指していると信じています。
こういったインクルーシブな社会を形成するためには、インクルーシブ教育が不可欠であります。子どもから大人まで、全ての人がこれを学ぶ必要があります。世界では国によって取組方も全く異なっています。これまでインクルーシブ教育についてディスカッションを重ねてきましたが、再度この点について、以下質問をします。
質問1の1、インクルーシブ教育システムについて。第六期長期計画の用語集にインクルーシブ教育システムがあります。インクルーシブやインクルーシブ教育は、この用語集にはありません。インクルーシブ教育システムということが特別な概念なので、あえて用語集に掲載していると想像されます。改めて、言葉の定義とその実態について確認するために質問します。
1)インクルーシブ教育システムとフルインクルーシブ教育の違いについて伺います。
2)インクルーシブ教育システムの実施状況について伺います。神奈川県愛甲郡愛川町で実施されているインクルーシブ教育について御紹介いたします。愛川町教育委員会指導室の室長、菅沼知香子様は次のように説明しています。外国にルーツのある子どもたちが多いのも事実ですが、最近では発達障害など特別な支援を要する子どもたちが非常に多くなってきている現実もあります。外国にルーツのある子どもたちと同時に、そうした子どもたちへのサポートも必要になってきています。そのため、愛川町では、2年ほど前からインクルーシブサポーターを配置しています。支援が必要な子どものために配置される人たちは、介助員と呼ばれていることが多いようです。しかし、愛川町ではインクルーシブサポーターと名づけています。介助員というと、対象の子の面倒だけを見ていればいいと解釈されますが、インクルーシブサポーターは、対象の子だけでなく、困難な場面で困っている子どもたちをサポートすることになっています。そこには、外国にルーツを持つ子どもたちや特別支援の子どもたちだけでなく、日本人の普通の子どもたちも含まれています。つまり、特定の子だけを対象にするスポットのインクルーシブ教育ではなく、面のインクルーシブ教育ですと説明をしています。
質問の3)です。今御紹介した、面のインクルーシブ教育についての御見解を伺います。
質問1の2です。特別支援学級について。次に、具体的な教育として、日本で実施している特別支援学級について考えていきます。
1)特別支援学級と特別支援学校の違いについて伺います。子どもの進路を考えるとき、特別支援学級、特別支援学校があり、もちろん通常級への登校という選択肢もあります。
2)です。特別支援学級を選択、決定するプロセスについて伺います。この質問については、昨日の山本議員の一般質問で全く同じ質疑がありました。その答弁は、まず就学相談があり、本人、御家族と相談員との意見が合わない場合は、さらに面談、検査、観察を経て、委員会で検討を行う。その結果を報告し、それでも方向性が合わない場合は、校長先生との面談となるというものでした。この答弁をベースに質問をいたします。
(1)です。この委員会では何を検討するのか。その際の検討の基準はどう定められているのか。
(2)です。委員会における結果とはどのようなものを指しているのか。
(3)校長先生とは、どの学校の校長先生なのか。
質問の3)です。武蔵野市の特別支援学級の課題について伺います。
次に、大きな2番、安全・安心のまちづくりについて。
武蔵野市つきまとい勧誘行為の防止及び路上宣伝行為等の適正化に関する条例──以下、「条例」と言います──が改正強化されました。さらに、条例に基づく勧誘行為等の適正化特定地区──以下、「特定地区」と言います──の区域の見直しの検討が続いています。市民意見交換会では、近隣にお住まいの住民の皆さんから厳しい発言が相次ぎました。条例改正以来、一般質問において市長のお考えを伺ってきました。これまでのやり取りを振り返ってみると、令和5年第1回定例会では、警察発表の刑法犯件数が激減しているというデータをお示しいただき、今御指摘の場所──これは、かつて近鉄裏と呼ばれていた地域のことですけれども──を昔から知っている方からすると、今も声はかけられるけど、昔は腕を引っ張られたり、連れ込まれたり、もうもっとひどい状態で、非常に体感治安も悪かったことから考えると、本当によくなったというふうに言ってくださる方もいらっしゃるので、安全・安心なまちづくりの、これがゴールだというのはとても難しいのかなと思っておりますが、最初にお答えしたように、条例を変えて制定しておりますので、その条例にのっとった、客引き、客待ち等の禁止行為が、行いづらい、行われないような形というのは、目指していきたいと思っておりますとの御見解をいただいております。しかし、昔に比べてかなり好転してきているものの、今の状態をよしとしない意見や、また悪化してしまうのではないかという不安の声も聞こえてきます。
第2回定例会においては、令和5年度からブルーキャップの活動時間を延長するとともに、深夜、早朝に活動する吉祥寺ミッドナイトパトロール隊においても、従来の安全パトロールに加えて、客引き行為等に対する指導等ができるよう制度を変更し、より体制を強化いたしました。またブルーキャップの活動人数について、客引き行為等を行う者が多い金曜日の夜間などに、より多くの隊員を配置するなど、曜日や時間帯による人数を工夫し、より効果的なパトロールが実施できるよう運用しています。付きまとい勧誘行為など禁止行為に対しては、毅然とした態度で注意や指導を行うとともに、条例について知らない者に対しては丁寧に内容を説明するなど、粘り強く活動を行うことで、禁止行為が行いづらい環境づくりを目指してまいりますとの御見解をいただきました。
これに対し、ブルーキャップ、ミッドナイトパトロールについて、今のやり方では実効性がないのではないかという意見が出ています。条例に定められている指導、警告、勧告、公表について、実際に行われているのか、疑問に感じている市民も多いです。特に公表については、これまで一件も実績がないことに対する疑問も出ています。
本条例について、以下質問をします。
質問2の1、安全・安心のまちづくりについて。
1)本条例に基づく改正後の施策と実績について伺います。
2)特定地区の現状と範囲の見直しについて伺います。
3)本条例の実効性についての見解を伺います。
4)罰金、過料、科料に関する考え方について伺います。
質問2の2、ブルーキャップ、ミッドナイトパトロールについて。
1)ブルーキャップとミッドナイトパトロールの現状について伺います。
2)ブルーキャップとミッドナイトパトロールの課題について伺います。
3)ブルーキャップ、ミッドナイトパトロールの人員の強化について、お考えを伺います。
大きな3番です。適正な契約について。
令和4年第4回定例会において、定期監査の指摘事項について質問をし、それに対し、市長より以下の回答をいただきました。定期監査報告書の中から各課に共通する課題等をピックアップし、全職員が改めてルールを確認し、適正な事務処理に努めるよう周知を図っています。定期監査の指摘事項の確認を徹底し、改善に努めてまいります。また、主管課の契約事務担当者、課長補佐、係長、管理職向けなどの職層に応じた研修を実施、より理解しやすいようにマニュアルの見直しを行うほか、業者指定がある場合に指定理由の入力がなく処理を進める場合に、エラーの注意喚起を表示するなどのシステムの改修を行い、適正な契約事務の執行に努めてまいります。このときは、令和3年度分までの結果をベースにした質疑でした。既に令和4年度分の結果が出ていますので、それを含め、以下質問をいたします。
質問3の1、定期監査の結果について。
1)定期監査の指摘事項の現状について伺います。
2)改善されない現状の評価について伺います。
質問3の2、今後の取組について。
上述のとおり、令和4年の定例会における方策の説明は、共通課題のピックアップ、全職員への周知、階層に応じた研修の実施、マニュアルの見直し、システムの改修が挙げられていました。これらについて、以下質問します。
今、答弁をいただいていた中の具体的な改善の方策の現在の実施状況について伺います。
2)です。実施している研修の内容と、その効果について伺います。
以上、壇上からの質問といたします。よろしくお願いいたします。
-
34:
◯市 長(松下玲子君) 宮代一利議員の一般質問に順にお答えをしてまいります。
まず、私からは2の1の1)についてです。客引き、客待ちが多かった吉祥寺駅南口の階段を降りた付近について、重点的に対応した結果、ブルーキャップ活動時間内での客引き行為を行う者はいなくなり、一定の成果が出ていると考えております。令和4年度の実績といたしまして、ブルーキャップによる禁止行為に対する口頭注意は2,217件、禁止行為に対する指導は5件、禁止行為に対する警告は4件、路上宣伝行為に対する注意等は278件です。
続いて2)についてです。これまでは、執拗な付きまとい勧誘行為のみを禁止行為としていたため、主に人通りの多い吉祥寺駅北口のサンロードや、南口のパークロードといった中心エリアを指定していました。令和4年4月から、新たに飲食店や風俗営業店の客引き行為等も禁止行為に加えたことにより、それらの実態を踏まえた上で、区域を見直す必要があると考えております。区域見直しに当たっては、吉祥寺活性化協議会、商店会連合会や市民意見交換会における意見も踏まえて区域変更案を検討いたしました。付きまとい勧誘行為や客引き行為等の禁止行為に至るおそれがある行為が他の地域より多く認められる地域やその周辺地域を追加する区域変更案を作成し、8月25日に開催をした環境浄化審議会に諮問を行いました。審議会においては、全委員の賛同を得ました。今後、審議会からの答申を受け、地区指定について手続を進めてまいります。
3)、4)は関連するため、まとめてお答えをいたします。昨年4月の改正条例の施行により、客引き行為、スカウト行為及び客待ち行為を新たに禁止行為として追加した効果は一定あったと考えております。大きな繁華街を持つ自治体においても、過料を設けず対応し、効果が出ているとも聞いています。過料を科さずとも、本条例に基づく警告等の運用で効果があると認識をしております。本市としましては、現在の条例で定められている指導、警告、勧告等に該当する行為を現認できた場合は、見過ごさず、適切に処置を行い、粘り強く注意をすることで、客引き、スカウト等が活動しづらい状況をつくっていきたいと考えております。
次に、2の2の1)、2)は関連するため、まとめてお答えをいたします。令和5年度から、ブルーキャップの活動時間を延長するとともに、深夜、早朝に活動する吉祥寺ミッドナイトパトロール隊においても、従来の安全パトロールに加えて、客引き行為等に対する指導等ができるよう制度を変更し、より体制を強化しました。ブルーキャップと市職員において定期的に協議を行いつつ、パトロール方法について状況に応じた改善を加えながら対応を行っています。評価や感謝の声をいただく一方で、まだまちの状況は改善していないという厳しいお声をいただくことも事実であります。ブルーキャップがいる前では明らかな客引き行為を行わないことや、客待ち行為の認定の難しさなどから、指導、警告等の件数には表れていないですが、客引き行為等と思われる現場を確認した際は、口頭注意を粘り強く行うことで、禁止行為が行いづらい環境を目指して活動を行っております。
続きまして、3)についてです。客引き行為等の状況を注視しながら、曜日や時間帯の隊員の人数配分について、事業者と調整を行いつつ、柔軟に対応しています。現在の体制及び制度の中で最善を尽くし、その上で改善しない場合は、必要に応じて隊員の人数増加について検討を行ってまいります。
続いて、3の1の1)についてです。特命随意契約に係る令和4年度の指摘件数は13件で、内容は、随意契約とした根拠法令の号数や、契約した業者を指定した具体的な理由の記載が漏れていたものが7件のほか、収入印紙の添付漏れ、予定価格、比較価格の記載漏れ及び私印決裁されていたものが6件です。令和3年度の指摘件数は7件で、内容は、見積り合わせを2者以上でしなければならないところを、1者でしか行っていなかったものが1件のほか、随意契約とした根拠法令の号数や、契約した業者を指定した具体的な理由の記載漏れが6件でした。令和2年度の指摘件数は13件で、内容は、分割発注に見えるものが1件、見積り合わせの業者数が不足するものが4件のほか、指定理由の記載漏れ、随意契約とした根拠法令の記載誤りや記載漏れ、契約した業者を指定した具体的な理由の記載漏れが8件です。令和元年度の指摘件数は9件、内容は、分割発注に見えるものが2件のほか、指定理由の記載誤りや記載漏れが7件でありました。
2)についてです。監査指摘事項は、例年同じような誤りがあることについて残念に思っています。改めて課内のチェック体制の強化、契約事務研修等の受講を含め、契約事務の理解を繰り返し促すとともに、法令、要綱、マニュアル等を確認し、適正な事務処理を行うことを徹底していくなど、不断の努力を続けていく必要があると考えております。
続きまして、3の2の1)、2)は関連するため、まとめてお答えをいたします。庁内における研修として、新任職員向け研修、担当者向け契約事務研修、課長補佐、係長及び新任管理職に向けたリスクマネジメント研修を別個に行い、それぞれの職層に応じた4つの研修をきめ細かく展開しています。それらの効果については、参加者アンケートで多くの職員から、参考になったと回答を得ています。契約関連のマニュアルについて、今年度はプロポーザル実施手続を一部改定するなど、より分かりやすいマニュアルになるよう適宜見直しを行っています。また、指摘の多い指定理由の入力漏れについて、入力がなく処理を進める場合にエラーの注意喚起を表示するシステムの改修を令和5年度に行ったため、今後の入力漏れは解消される見通しです。職員ポータルにおいて、契約等で不明なことがあれば、簡単に確認することができるオンライン問合せシステムも運用しています。このように、研修やシステム改修などを重ね、また、各課でのチェック体制を整えることなど、庁内全体で契約に関する理解を深めていくことが重要と考えます。
他の質問については教育長からお答えをいたします。 -
35:
◯教育長(竹内道則君) 私からは、大きい御質問の1番目、インクルーシブ教育について順次お答えいたします。
インクルーシブ教育システムと、いわゆるフルインクルーシブ教育の違いについての御質問ですが、最初に、インクルーシブ教育システムもフルインクルーシブ教育システムも、その目的は共生社会の実現を目指すものであるということをまず確認しておきたいと思います。フルインクルーシブ教育は、特別支援学校や特別支援学級などを設けず、障害のあるなしにかかわらず、全ての児童生徒が同じ場で共に学ぶ教育のことと認識をしております。インクルーシブ教育システムは、児童生徒の社会的自立に向け、一人一人の教育的ニーズに対応するため、通常学級のほかに特別支援教室や通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった連続性のある多様な学びの場を用意している教育のことでございます。
そして、そのインクルーシブ教育システムの実施状況についての御質問ですが、市では、インクルーシブ教育システムの理念である、障害のある子どもと障害のない子どもが同じ場で共に学ぶことを追求するために、特別支援学校と地域の学校の副籍交流の実施や、通常学級と特別支援学級の交流及び共同学習を進めるために支援員の配置を行うなど、そういったことを行って、障害のある子の個別の教育的ニーズに応えるための連続性のある多様な学びの場づくりや、ほかの児童生徒の障害理解を推進しているところです。
そして、御紹介のあった、面のインクルーシブ教育ということで、神奈川県の愛川町の例を御紹介いただきました。障害のある子どもがいるから支援をするというのではなく、子どもが困っている場面を支援するという視点は、社会的障壁という障害の捉え方や個々の教育的ニーズにおいても、個別最適な学びにもつながる興味深い考え方であると思います。
特別支援学級と特別支援学校の違いについてです。特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者または病弱者を対象に、小・中学校に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上や生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な知識、技能を身につけることを目的として、都道府県が設置する学校です。特別支援学校については、対象となる障害の程度が定められております。特別支援学級についてですが、障害の程度が特別支援学校の対象には該当しない視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者、言語障害者、自閉症、情緒障害者に対して、障害による学習または生活上の困難を克服するための教育を行うことを目的に、小・中学校等に置く学級です。
そして、特別支援学級を選択、決定をするプロセスについてです。他の議員の質問にもお答えしましたが、就学相談を受けていただき、特別支援学級の見学や、本人、保護者の意見、就学支援委員会の検討結果を踏まえて、総合的な観点から決定をいたします。なお、壇上から御質問のあった基準については、特別支援学校では定めているところですが、特別支援学級については、個別の判断になるところですので、今申し上げた総合的な観点からの決定ということになります。
それから、面談を行う校長については、保護者が就学を希望する学区の小学校、中学校の校長でございます。
そして、特別支援学級の課題としては、特別支援学級の中にも様々な教育的ニーズの児童生徒がいるため、個別の対応が重要になっているものと認識をしております。
先ほど答弁申し上げた交流及び共同学習ですが、特別支援学級と通常学級の連続性を確保し、障害の有無にかかわらず、児童生徒が相互理解し、人間関係を広げ、社会性や豊かな人間性を育むために、今後も推進すべきと考えております。現在、その実施をサポートする支援員について、同じ時間に複数の児童に支援が必要となる状況が生じており、支援員の拡充は課題になっているものと認識しております。
以上です。 -
36:
◯6 番(宮代一利君) 様々御回答いただきありがとうございました。
先に安全・安心なまちづくりと契約の話をやります。先ほどのデータをお聞きして、注意については2,000件を超えてやっていただいていると。確かに、現地では非常にたくさんのブルーキャップが出て、それからまた、ある意味、私から見て適切なアプローチをしてくれているなというふうには感じていますが、やはり指摘されているのは、いわゆるいたちごっこ、いなくなったら湧いてくるという、それを繰り返しているなというところはどうしても否めないというところがあります。主に、やはり一番最初のこの話の始まりが吉祥寺の南口から始まっていたので、先ほど出てきた意見の中には北口側、いわゆる今でいうヨドバシ裏と言われているところですけど、そこが手薄なのではないのかなというような意見、それに対する不安みたいなものが出てきているので、1つまず、南口と北口のすみ分けというか、今どんなふうにブルーキャップさんのほうでやっているのかということについて、分かれば教えていただきたいなというふうに思っています。
それから、今アプローチとしては適正かな、適切かなというふうに感じるという一方で、やはり厳しい指摘の中には、前にも御指摘しましたけど、なれ合い、要するに談笑してしまっている場面とかがあるのです。お友達になってしまっているのです。若いブルーキャップの方たちもいますので、客引きしている方たちの中にも若い人がいて、お話をしているという実態があって、市民の皆様が横を通っていくときにそういった姿を見ると、やはりちょっと疑問に感じるというところがあるのではないかなという事象を私も見ています。なので、やはりその辺、以前の御答弁の中にも、毅然とした態度で臨むというようなこともあって、もう少しこれからも実態についての追求をしていただいて、きちんとデータを取りながら、ブルーキャップさんとどういうふうに会話をしていくのかということももう少し深めていただきたいなというふうに思っているので、ぜひ御検討いただきたいと思いますが、この辺のことについて、ぜひ御見解を伺いたいと思います。
それからもう一つ、先ほどのコメントの中に、客待ちの認定の難しさという話があったのですけど、確かにそうなのです。そこに立っているだけだと、客待ちでしょうと言えないところがあるのですけど、それでも、インカムを着けてしゃべっていますから、どう見ても一目瞭然でこの方はそういう仕事をしようとしてここに来ていると分かるのですけど、何かここは今後、どういうふうに認定していくのかということを工夫していっていただきたいなというふうに思っています。
それから、人員の強化については、配分については柔軟に考えていただけると。今日、市長からは必要に応じてというお話をいただきましたので、今後、現状、これからの流れも見ながら、場合によっては人員を強化するということもお考えがあるというふうに受け止めましたので、それで間違いがないかどうかについて一応確認をもう一度させてください。
それから、契約のほうですけれども、今日、これはまた最初の市長の答弁で、同じようなことがずっと行われ続けていて残念だというお言葉をいただきましたので、安心しました。この状態で仕方がないのではないかと言われてしまうと、全部は絶対一掃されないねというふうに思っていて、やはりこれは、確かに人間が関わっていることだからヒューマンエラーはあり得ると思いますけど、あまりにも同じことが繰り返されているということの印象が否めないので、何年も何年もずっと同じような数値と回数で同じようなことが行われていますから、これは確実になくすというふうにしていただきたいと思っていますので、ぜひお願いしたいと思います。こちらは要望にします。
それから、システムの改修はなされたという御説明だったと思うので、全部の情報がそろわないとエラーが出てきてしまって、はねて戻ってくるという形になったのだと思いますので、そこはいいなというふうに思う一方で、逆に、システムを通ったから大丈夫、要するに最も注目すべきは随契ですけど、随契は何かルールのどこかを押しておけば進むよねという感覚にならないように、本当にこの随意契約を選んでいることがどういう根拠で、なぜこういうことをしているのかということについては、きちんとこれからもずっとみんなに伝わるように研修を続けていただきたいなというふうに思います。やはり随意契約は、市民から見ると、見えにくいところは不透明な部分というふうに感じてしまうところがあるので、できれば、本当は相見積りをきちんと取っていただいて進めていただきたいところですが、様々な理由で随意契約を選んでいるという部分があって、それにはそれぞれ理由があると思うのですが、その理由が適正な理由なのかどうかということについては、今後も検証は続けていただきたいと思いますが、御見解を伺いたいと思います。
以上、取りあえずお願いいたします。 -
37:
◯市 長(松下玲子君) 再質問にお答えをいたします。2項目それぞれからいただきましたので、まず、安全・安心のまちづくりに関してですが、北口も南口も同様にブルーキャップが活動をしております。ルートについての御質問があったのですが、こちらは、ブルーキャップと市職員において定期的に協議を行いつつ、実際のパトロール方法について状況に応じた改善を加えながら対応を行っておりますので、この場で、こんなルートで回っていますとかこっちに行っていますというのは、ちょっとお答えいたしかねます。適宜事業者と定期的に協議を行いながら、改善を加えながら、パトロール方法について対応を行っています。
またその上で、なれ合っているのではないか、そういうふうに見えたよという御指摘でした。注意喚起を、まず定期的な協議を行っておりますので、そうした中でも、誤解を与えることがないように、緊張感を持ってしっかりと活動してもらうように注意をしていきたいと思っております。
続いて、契約に関しましては、おっしゃるように、やはり随意契約とした根拠法令をしっかり示さないと、それは検証もできませんので、そこの指摘の部分はしっかりと改善していくようにしたいと思いますし、システムの改修は令和5年度になりましたので、今お答えした中は令和4年度までの件数ですので、今後5年度に、システム上、エラーの注意喚起で先に処理が進めないようにしていますので、そうした中で、またしっかりと契約について取り組みたいというふうに思っております。
以上です。 -
38:
◯6 番(宮代一利君) ありがとうございます。今度、令和5年度の対象になっている監査の結果を楽しみに待ちたいと思います。いつかゼロになる日が来るように頑張り続けていただきたいなと思います。
それから、実は何人かのブルーキャップさんとは私も直接お話をすることがあって、僕たちは権限がないのですというふうに言っているのです。注意がしにくいと。ただこういうふうな条例がありますと説明することしかできなくて、それ以上の権限がないというふうな思いでブルーキャップさん自身が取り組んでいるという御意見が聞こえてきています。ただ一方で、今、全員とやっているわけではないでしょうけど、協議をしたり、改善をしたりというふうにして取り組んでいただいているということなので、現場のほうにはそういった声もあるのだということも知っていただいた上で、これからの協議も続けていただきたいなというふうに思います。とにかく実効を上げて、地元の市民の皆さんが安心していただけるような、そしてやはりブルーキャップにやってもらってよかったよねというふうに納得してもらえるような形に最後は持っていかなければいけないというふうに思いますので、お願いします。市民の皆さんも関心を持っていますし、議員も議連をつくって取り組むというふうにしているので、やはりブルーキャップというものでやっているからもう大丈夫ということではなくて、関わっているみんながそれぞれの立場で進んでいくことが非常に重要だと思いますので、私たちも頑張りますので、本当にいいまちづくりを、そして市民の方に安心していただけるようになってほしいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
それでは次に、インクルーシブの件ですけれども、まず、インクルーシブ教育システムとフルインクルーシブ教育の共通の目的が共生社会の形成ですという、そこは同じですということがまず確認できてよかったと思うのですが、インクルーシブ教育システムは、これは日本のシステムですよね。日本におけるこういうインクルーシブに対する取組と呼んでいるシステムなのではないかなというふうに私は理解しているのですが、一方で、フルインクルーシブシステムというのは、今日本では取り入れることができていなくて、海外の幾つかの国でこういったことに取り組んでいる。よくイタリアがすごく先進国だというふうに言われているのですけど。私の疑問というか、何で日本はこの形になってしまっているのか、縛られてしまっていて、ここから抜け出すことはできないのかということをちょっと今思っています。
特別支援学校とか特別支援学級がよくないというふうに申し上げているのではないです。障害をお持ちの方に対しては、合理的な配慮、リーズナブル・アコモデーションが必要なのですというのは皆さん分かっていて、その合理的な配慮というもののツールとして特別支援学校、特別支援学級があるというストーリーなのです。ところが、先ほどの御説明のとおり、学校を選ぶときに、最初にまず就学相談をして、普通に相談をしに行っているのに、いつの間にか委員会にまでかかった上に、結果が通達されて、最終的に合わなかったら校長先生ともう1回面談しますと。私がもう少し知りたいのは、この校長先生と面談した後に、最後にどういうふうな結果になるのか知りたいのです。最後の最後までずっと平行線で行ったときに、例えば通常級に行きたいですと言い続けている親御さん、本人さんがいるときに、どうやら何かプロセスを踏んでいるけど、最後まで平行線のまま行った場合にどんなふうになっていくのかということについて、教えていただきたいと思います。お願いします。 -
39:
◯教育長(竹内道則君) インクルーシブ教育システムですが、議員御指摘のとおり、日本におけるインクルーシブ教育システムは、日本における内容、定義だと思います。そして、それについては、日本の教育の制度の様々な沿革からこのようなインクルーシブ教育システムになってきたものと思いますし、それは、外国との比較でいっても、日本の学校教育の内容の違いあるいはその形態の違いなどから、現在の形が最も適しているだろうということで、同様の共生社会の実現に向けた形として取られているものと認識しています。
そして、就学先の決定については、就学委員会というものを設けているというのは、これは客観的に、あるいは専門的な見地から見るということで、そういった枠組みを設けているわけですけども、最終的に御希望とその委員会の決定が沿わないときには、先ほど、学区の小学校、中学校の校長との面談も行うというふうにありましたけれども、その中では、様々な事情、個別の判断がありますから、様々に相談をしていく中で、最終的には合理的配慮の提供の中で通学できるのではないか、就学できるのではないかという見通しが立てられる場合もありますし、保護者の御理解があって、やはり就学先については委員会が決定しようと。結論についてはどちらに行く場合もありますが、最終的に決まらないということはございませんので、そういった就学先の決定につながるような仕組みの流れとして御理解いただければと思います。 -
40:
◯6 番(宮代一利君) 難しい議論なのだと思います。ただ、1つこのお話の中で気になるのは、学校に行くのは子どもで、児童生徒さんであって、まず児童生徒が行きたいと思う学校であってほしい。それは、別に障害あるなしにかかわらずみんな行けるような──今なかなか行きづらい不登校とかという話も出てきたりもしている世の中において、なるべく多くの子どもたちが、児童生徒たちが行きたいと思う学校であってほしいというふうに思います。まずそれが第一だと思います。だからといって、子どもに向かって必ず行けといって大人が行かせるものでもないと思うのです。行きたいと思うことが一番大事なのではないかなというふうに思います。
これはちょっと見解というか、あれで申し上げますけど、よく一般的な話として、クラスの中で、例えば情緒不安定な子が通常級にいて、そこで走り回ったりすると授業が立ち行かなくなるだとか、それから、周りに迷惑がかかるだとかというふうな見解が出てくる場合があるということも聞いたりしているのですけど、周りの子どもたちに対して影響が出るというのはともかく、先生たちが授業がやりづらくなるという、私はそれを根拠にしてはいけないのではないか、大人の都合なのではないですかと思うのです。そこをうまく説明していってほしいなと。委員会には基準はない、総合的なというふうに言われると、それは何を示しているのかなというふうに疑問に思うところはあります。もちろん、ほぼ皆さんきちんと個別の対応をするために、それも適切な、必要な対応としてはいろいろやっている、合理的な配慮をしているのだというふうに信じていますけれども。もちろん、特別支援学校を積極的に選んでいるお子さんも、御家族もいる。特別支援学級を積極的に、うちの子は逆に、通常級に行ってしまったらパニックを起こしてしまうに違いないから、そこにいきなり入れるのではなくて、きちんと見てもらえる支援学校、支援学級のほうに行きたいというふうにして選んでいる方もたくさんいらっしゃると思うのです。だから、なかなか平行線でうまく話がまとまらないときに、どういうふうにそこを進めていくのかということにも気持ちを払っていただきたいなと、そこを見てほしいなというところがあるので、しつこくてすみません、もう1回御見解をいただきたい。
それから、日本のシステムについての疑問なのですけど、今の日本でいっているインクルーシブ教育システムというのは、インクルーシブの反対語はエクスクルーシブですよね。これは排除ですから、うちの学校には障害があって入れませんといって排除してしまうのはエクスクルーシブですけど、それはしていないと。しかしながら、特別支援学級、特別支援学校というものをつくったということは、そこにはセグリゲーションは起こっていますよね。セグリゲーションというのは分けるという意味です。通常学級でなくて、別のものがここに存在します、セグリゲーション。そのままセグったままで──ごめんなさい、セグるという言葉があるのはあるのですけど、セグリゲーションの状態のままでは、例えば昨日から地域移行、副籍交流の話が出ていますけど、うまくそっちが進まないだろうから、それをこっちの中に一緒に持ってきて統合します。そこでインテグレーションというふうになって社会が形成されるのです。ところが、セグリゲーションしてインテグレーションしている限りにおいては、本当のインクルーシブの形にはなり得ないのです。インクルーシブの形というのは、最初からこういうふうに構成員が決まっていて、その生徒たちがぽつぽつといっぱいいる中に、一人一人の障害を持っている生徒さんたちもこういうふうに入って、最初からごちゃ混ぜになっている状態が本当のインクルーシブだと思うのです。この先、セグリからインテグレーションにというふうにやっている今の日本のやり方を変えていかなければいけないのではないかというふうに私は考えています。それが本当のインクルーシブ教育につながるのではないかと思っているのですが、この考え方について、教育長の御見解を伺いたいです。 -
41:
◯教育長(竹内道則君) 就学先の決定については、あくまでも第一義的には、就学を希望されるお子さんの個別の教育的ニーズ、それにどのように合致するのかというのが第一番だと思います。それは、保護者の皆さんも学校側も前提としているものと思っています。その上で就学相談に当たっておると思います。
それから、インクルーシブ教育システムについては、ちょうど昨日、別な議員の御質問で、個別最適な学びが新しい学習指導要領の関連で出てきたのですけども、改めて学習指導要領の総則をちょっと今日見てみたのですけども、総則というのは一般原則です。その中に、特別な配慮を必要とする児童への指導というのが項目として立っているのです。これは、私の記憶では今回初めてこういう書き方をされているのですけども、その中の1番目に障害のある児童などへの指導があって、2番目に、海外から帰国した児童などの学校生活への適応や日本語の習得に困難がある児童に対する日本語指導が立っていて、3番目に不登校児童への配慮というふうに立っています。これはやはり、いろいろな困り感がある中で、個別に対応していこうということの項目の立て方の表れではないかなと思っていますので、基本的には、日本の場合にはインクルーシブ教育システムということで行っていますけれども、理念としては、個々の子どもの教育的ニーズに対応していこう、様々な障害がある、あるいは言葉が困難だとか、心理的な学校への親和性の課題があったりする、そういう中でのものに個々に寄り添っていこうということの表れなのだと思っています。
それから、以前に私、答弁申し上げたと思うのですけども、個々の教育的ニーズという中でいうと、障害のあるお子さんの社会的な自立という面でいうと、自立活動という領域がとても大事だと思っています。それは、学校の教室の授業の中で、基本的に一斉の授業をして、クラスのみんなが授業を受けている中で、その自立活動を授業の中でどういうふうに行うのか、それはやはり特別な時間を取って、場面を変えて行うということは必要なのだと思います。自立活動というのは、例えば人間関係の理解とか、コミュニケーションとか、環境の理解、心理的な安定、そういったことを個々に応じてサポートする、そういった社会的な自立のために必要なスキルを得ていくということですけども、それをその子は特別に行わなければならないときに、どこでそれを保障するのか。その個別の教育的ニーズとして特別支援学級があり、特別支援教室があり、通常級があり、その中で行き来をしてそれが保障できるということが、現在のインクルーシブ教育システムの中で行っていくことができるのではないかと考えています。
それから、市内で長年混合教育として取り組まれている学校がありますけれども、その学校も、学級は別に設定しているのですが、その上で十分な混合教育、交流が行われていますので、そういったことを見ても、必要に応じて場面があってしかるべきかなというふうに考えております。
以上です。 -
42:
◯6 番(宮代一利君) 丁寧な御説明、御見解ありがとうございました。そのとおりで、最終的には個々のニーズ、それは様々な場面、健常な子たちだってそれぞれみんなグラデーションがあって違うわけですから、それに合わせた教育は本当に大事だと思います。
一方で、いろいろ悩み苦しみを抱えている子に対して対応するためには、専門性、知識が必要な場面はすごく多いと思うので、そういったことの人たち、教育者を育てて増やしていくということもこれから取り組んでいく一つ大事なことなのではないかなと思います。
先ほどある学校がありますという話もあったのですけど、今回私は、すごく甘ったるいことを言いますけど、ベースキャンプを一緒にできないかなと。要するに、学校に行くときに一番最初に入る教室が一緒だよというふうにして、朝一番最初に学校に行ったときに、みんないろいろな子がいて、おはようという一言目を交わすのがそこのベースキャンプですと。そこから始まって、では授業が始まりますでもいいし、特別支援学級に行くでもいいし、ちょっと学校に行くにはまたバスに乗らなくてはいけないとかはありますけど、まず一番の最初の挨拶ができる場所をつくってほしいなというふうに私は思っているのです。そうすれば、大変そうだなと思っている子を認めれば、周りの生徒や児童たちは助ける手を差し伸べると思うというのが私の考えです。御見解をお願いいたします。 -
43:
◯教育長(竹内道則君) そういったことも参考にして考えてまいりたいと思います。